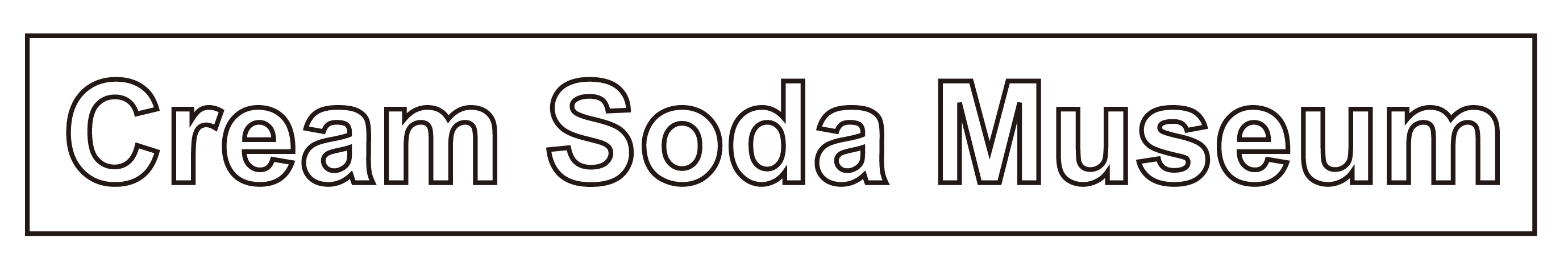Artist
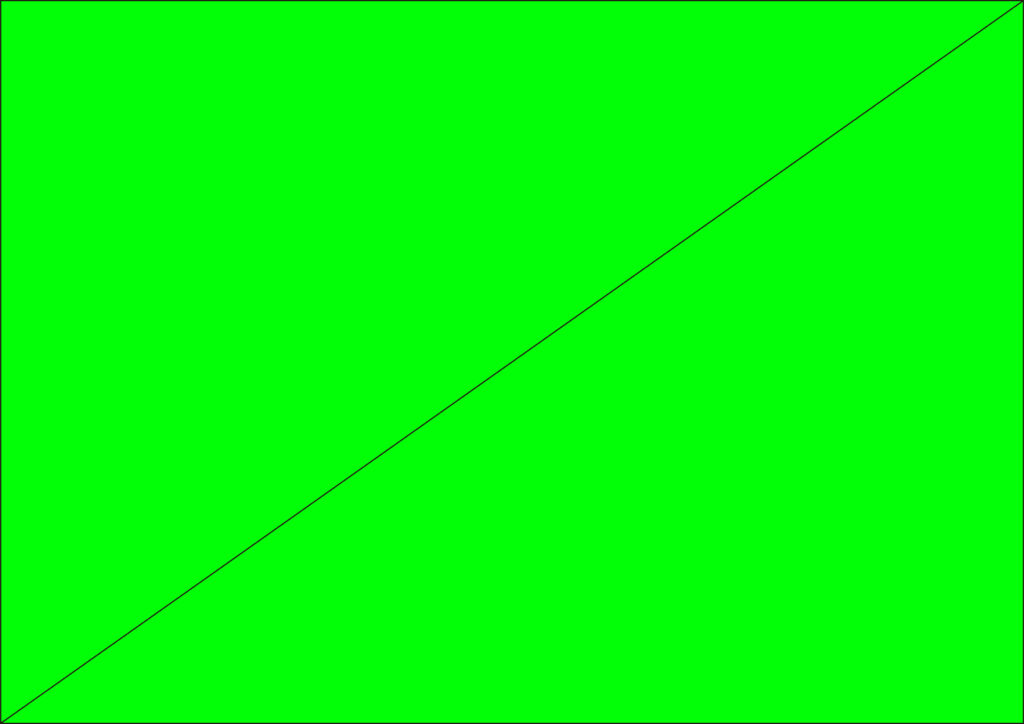
ティナ・セレク=ユリオス
アーティスト。植物学者。ナジームの炎の周囲にだけ生える特殊な藻類を「スフルリス」と名付ける。顕微鏡で見るとその藻類の胞子には、ナジーム語の音声波形に似た形状が存在することが発見され、植物を媒介とした「ナジームの植物言語=スフルリスランゲージ」が提唱される。 彼女はこの植物言語を用いた「沈黙の菜園」という展示空間を各地の植物園で開催している。
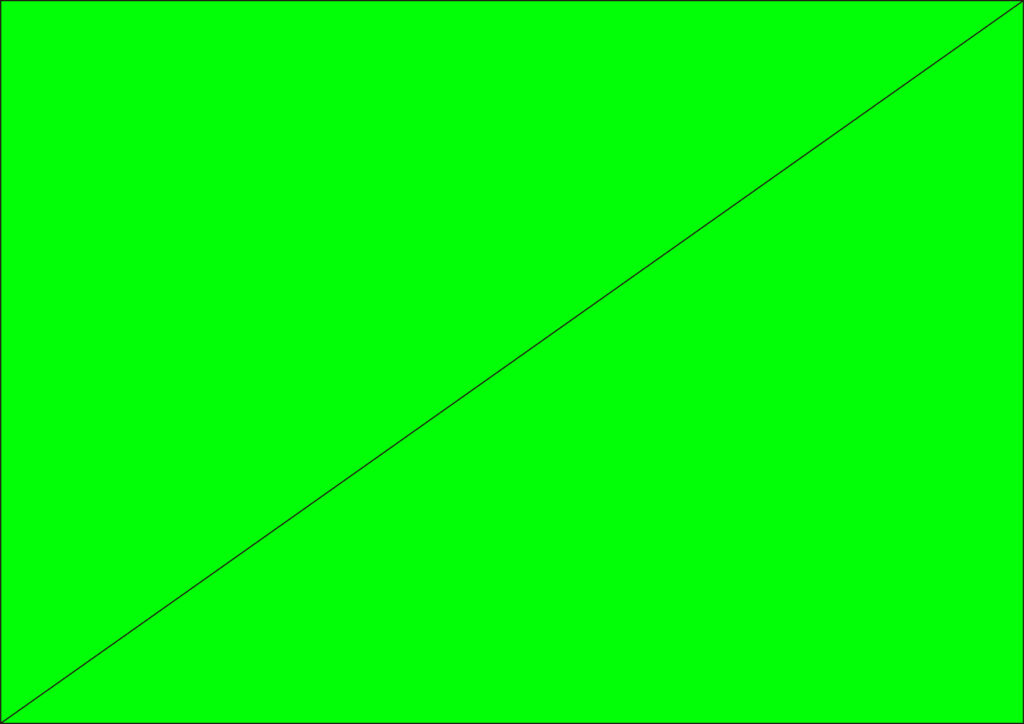
エフィゲニア・カランデュリ
アーティスト。探検家。科学者。2025年南極にて、手のひらサイズの謎の隕石を発見。その隕石を「エフィゲニア隕石」と名付ける。研究していくと、わずかに振動をしていることを発見。さらには、石に音を聴かせて、数回振ると未来にその音を送信することができ、石を回転させることによって再生することができることも発見した。例えば、数回石を振ることによって、現在の音を5分後の未来において聴くことができる。石を振れば振るほどより先の未来に音を送信することができる。
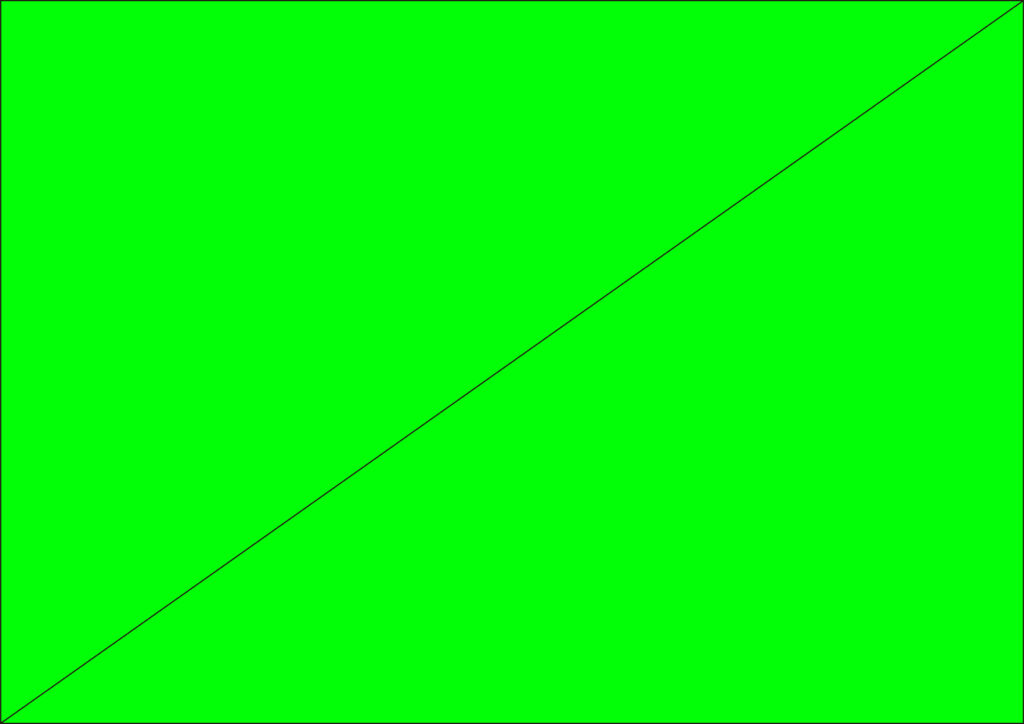
イェナカ・スブラマニヤム
アーティスト。イライジャ・チェンバレンの開発した未来写真AI「キョウト」の画像を解析し、様々な風景絵画を描いている。
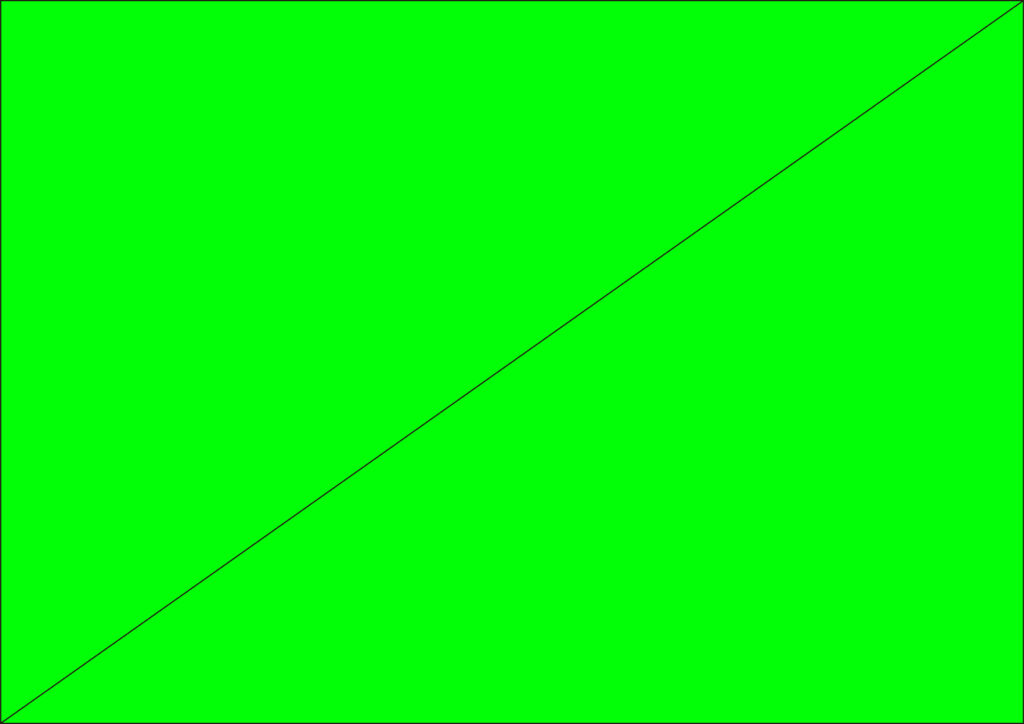
山川潔
アーティスト。発明家。「ナジームの炎」がリンゴを燃料にするとどんな方法をとっても永遠に炎を消すことができないという法則「イマヌエルの法則」を使用し、エネルギーの永久機関「ヤマカワシステム」を開発。2025年から持続可能なエネルギーシステムとして脚光を浴びている。
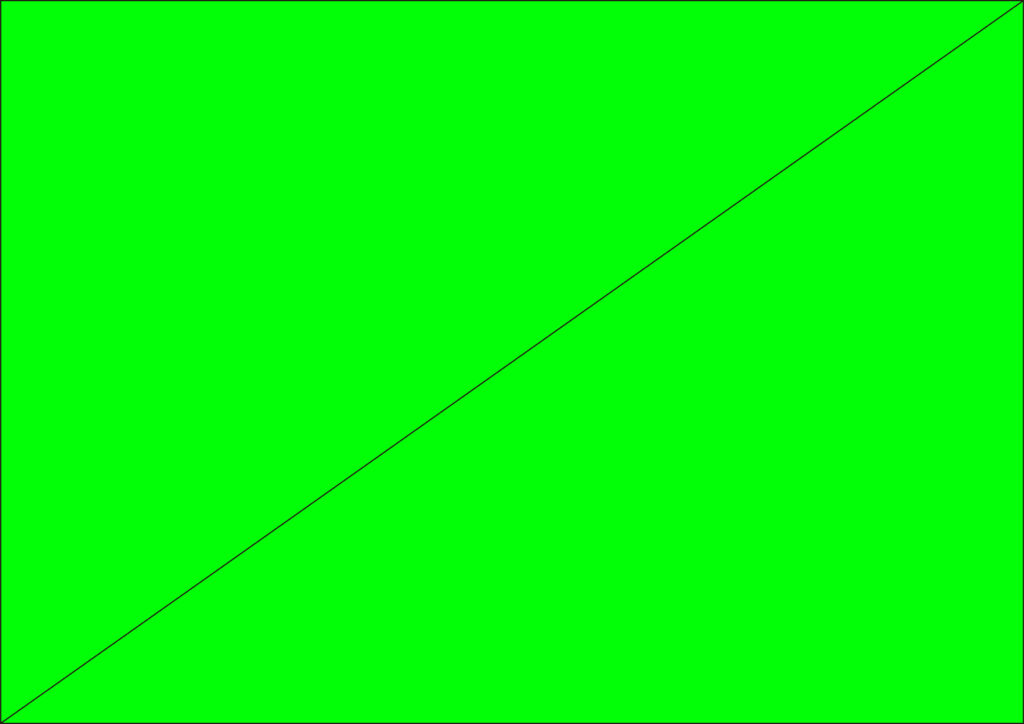
浜崎克衛
アーティスト。発明家。実業家。リンゴを燃料にするとどんな方法をとっても永遠にナジームの炎を消すことができないという法則イマヌエル・フェルマーバイヤーの「イマヌエルの法則」、そして山川潔による発明のエネルギーの永久機関「ヤマカワシステム」を使って、「克衛の湯」と名付けた人工温泉を開発。非常に優れたアンチエイジングの効果がある。
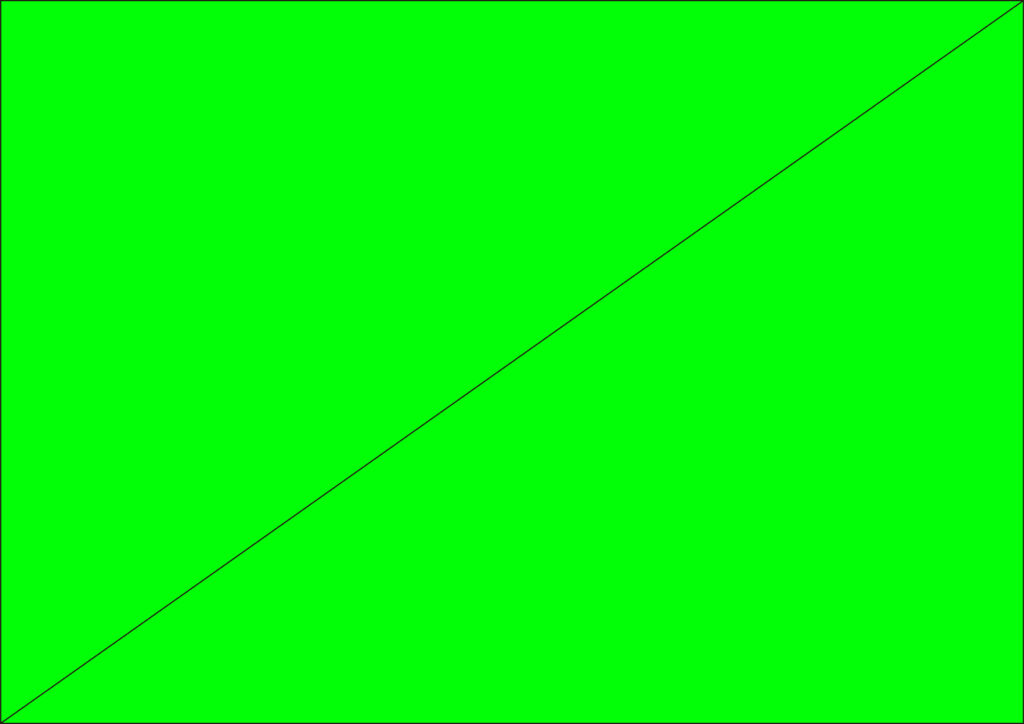
宇多田朔太郎
アーティスト。発明家。リンゴを燃料にするとどんな方法をとっても永遠にナジームの炎を消すことができないという法則イマヌエル・フェルマーバイヤーの「イマヌエルの法則」、そして山川潔による発明のエネルギーの永久機関「ヤマカワシステム」を使って、「克衛の湯」と名付けた人工温泉にコーヒーを混ぜることによって、不思議な音楽がその液体から聞こえることを発見。以来「ウタダコーヒー」と名付ける。味は薄まり飲むこともできるが、基本的に聴いて楽しむ人の方が多い。混ぜ方やコーヒー豆の産地、濃度などによって様々な音楽が流れる。
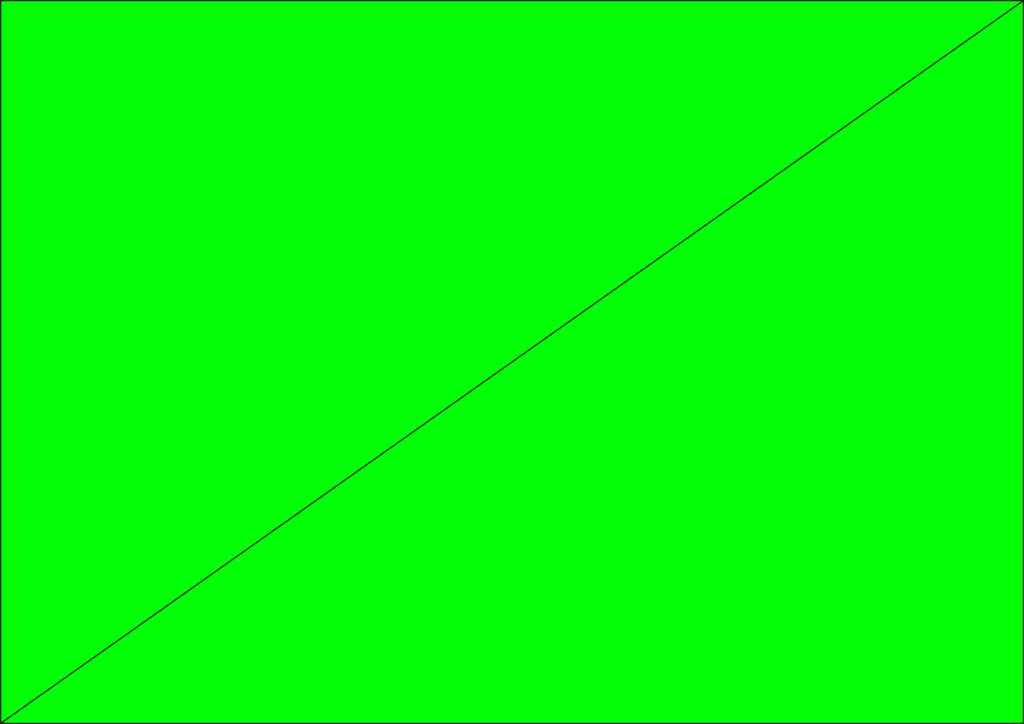
セオドア・ラウシェンバーグ
アーティスト。エンジニア。発明家。イライジャ・チェンバレンによる量子コンピューター型人工知能「オリガミ(Ubull Inc.)」をある日、ナジームの炎で焼いてみたところ、様々な風変わりな人間でもなく人工知能でもない超高度な知的生命体を自由自在に生成することができる人工知能をつくりだすことに成功した。その人工知能は、飼っていた象にちなんで「エレファント」と名付けた。生み出された知的生命体としては、例えば、アーティストとしては、サイラス・モーンやバター3などがいる。
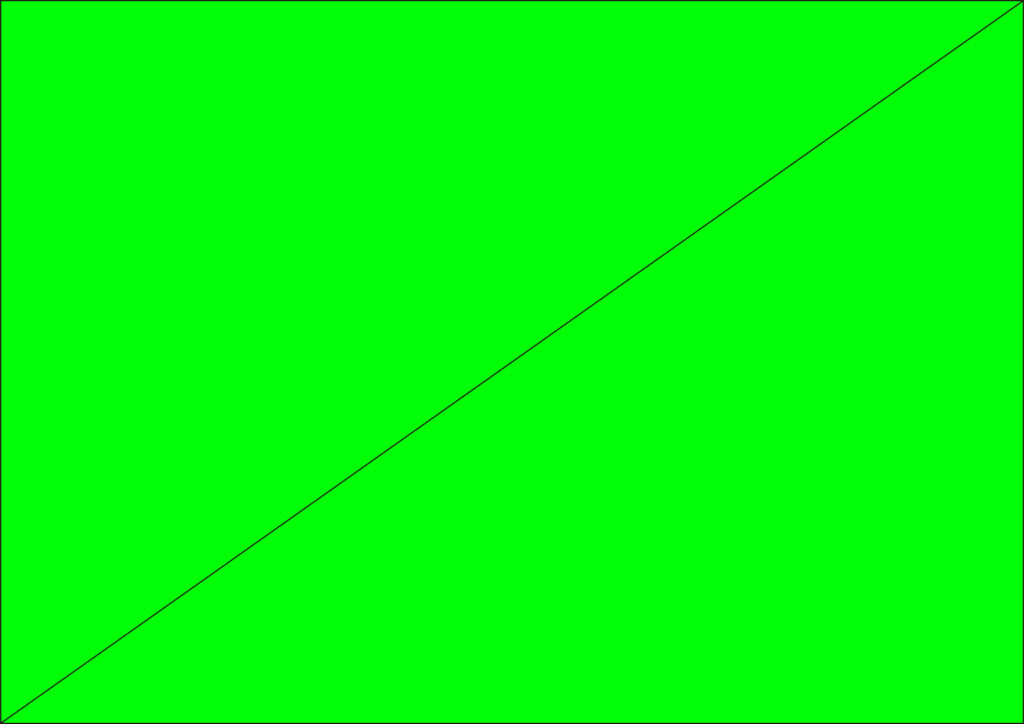
へへ・へペル・へへ
可逆性時間宇宙。アーティスト。この私たちの生きている宇宙とは異なる次元で発生し続けている宇宙。時間は、一直線のクロノス的時間で進むのではなく、非線形のカイロス的時間で起きている。この宇宙と一見関係ないようではあるが、音や光、色彩などによって、相互に影響を及ぼす可能性があることが考えられている。「へへ・へペル・へへ」とは古代エジプト語で「無限の中で、変化し、再び無限へ」という意味を持つ。
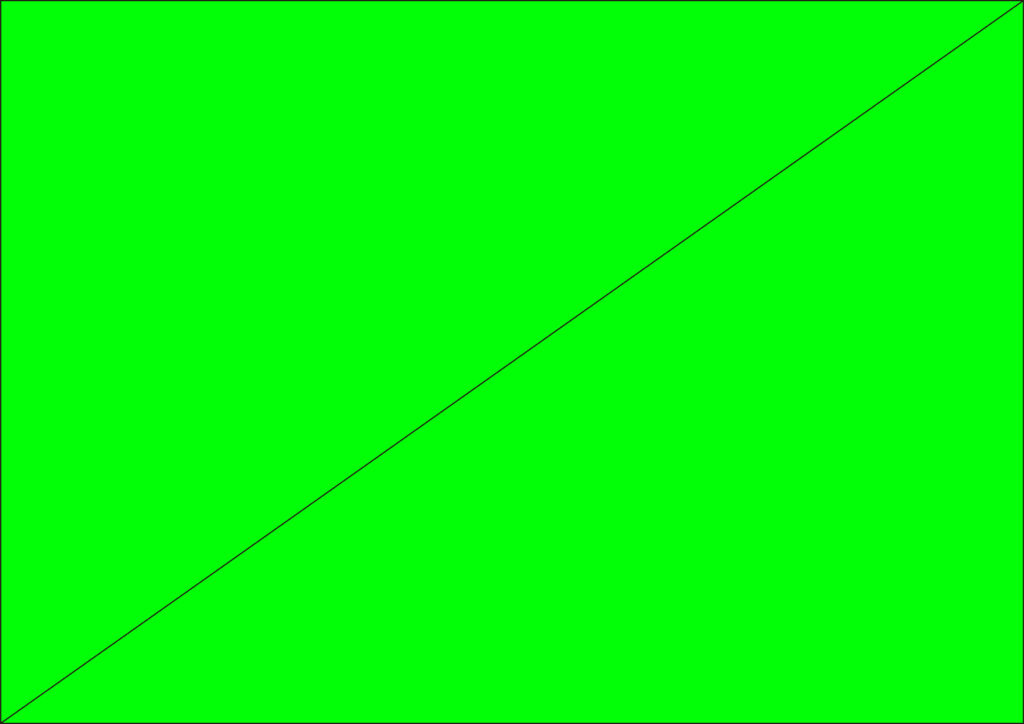
マルジャーナ・クワシメ
サウンドアーティスト。2025年南極にて、エフィゲニア・カランデュリによって発見された手のひらサイズの石を振って回すことによって音を奏でることができる謎の隕石「エフェゲニア隕石」を使って、サウンドパフォーマンスを行う。石を振る回数や回す速度、回し方の大きさにって、音を変化させ、古代から現代までの音を表現する。
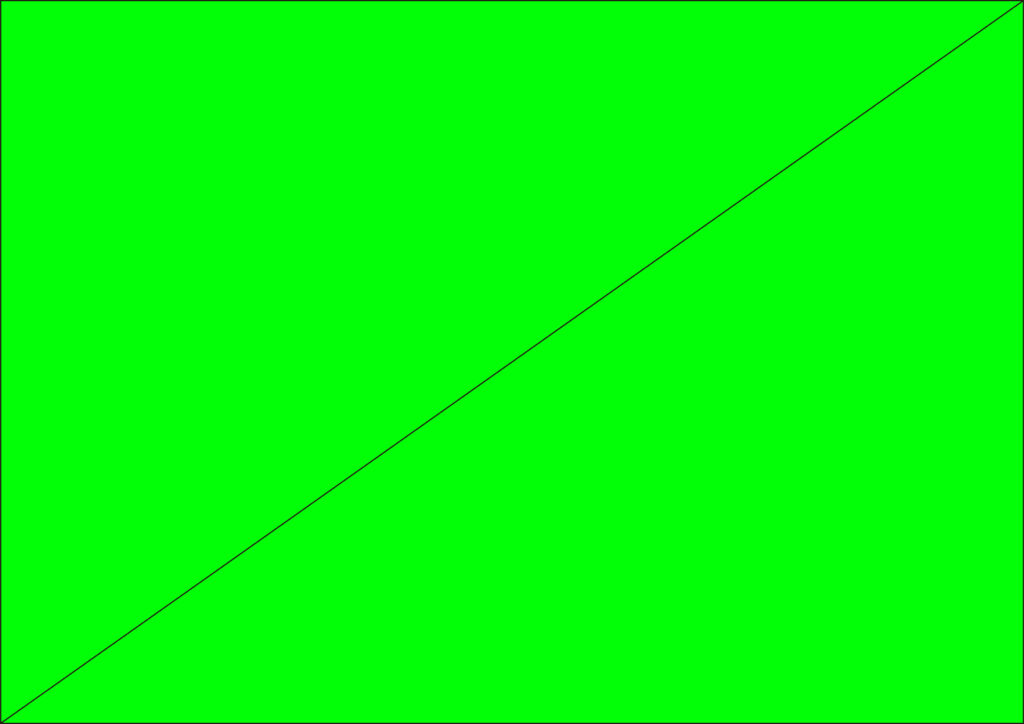
フローレンス・アプリン
アーティスト。実験家。ナジームの炎の近くに磁石を近づけると磁石が水のような透明な液体に変化することを発見。のちに「フローレンスの水」と呼ばれる。
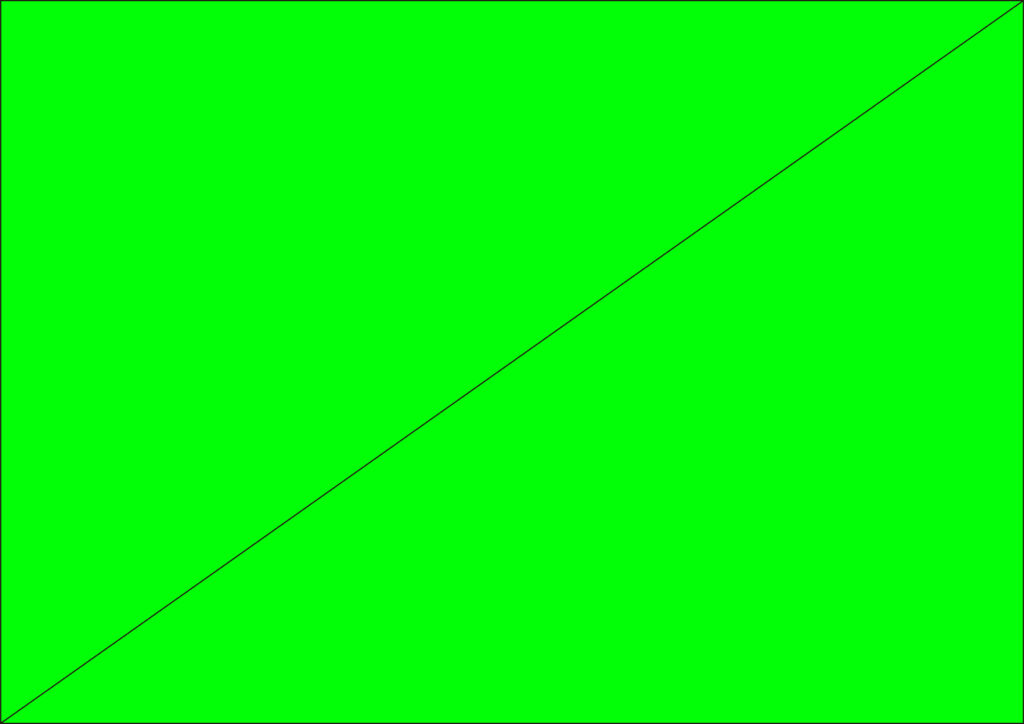
イモージェン・ペンハリゴン
アーティスト。ナジームの炎の近くに磁石を近づけ液体化した「フローレンスの水」を暗闇で光を通すと映像を投影することができることを発見。映像に主題のようなものはなく、抽象から具象、文字に至るまで様々なストーリーのない映像が投影されることが判明。のちに「イモージェンの光」と呼ばれる。
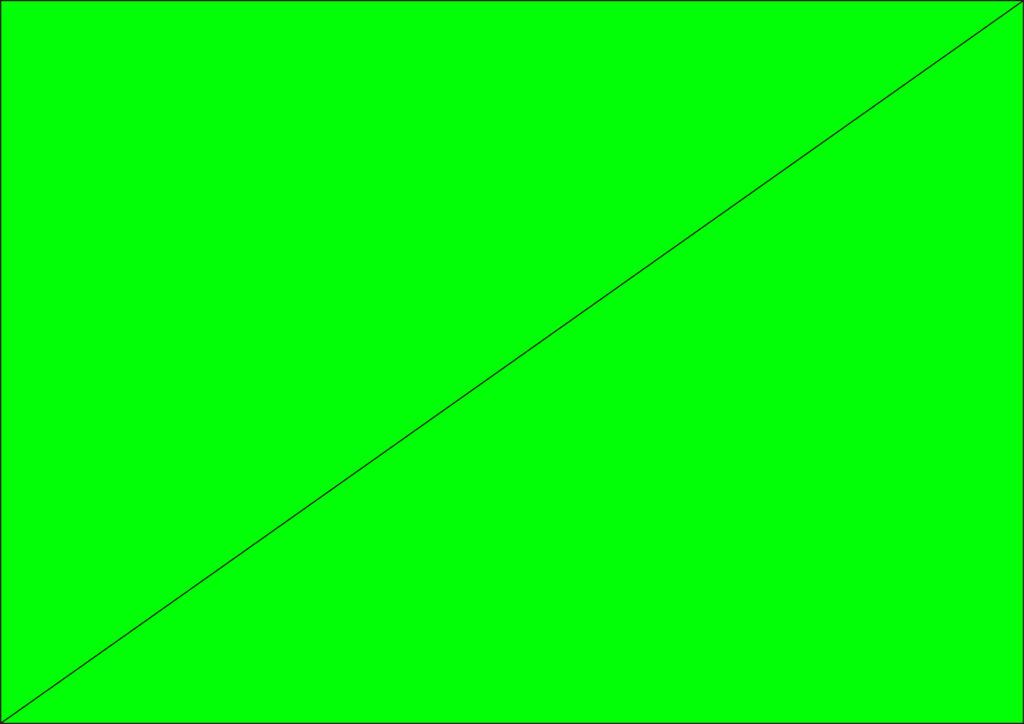
マリカ・ナスリーン
イモージェンの光の研究をさらに推し進め、フローレンスの水を媒介として、液体に小さな振動を与えると、距離の離れたフローレンスの水同士が同じ周波数で振動することが判明した。その振動から、新しい通信装置の開発を進めていった結果、人間の感情そのものを伝えられる機能性を持っていることも判明。「マリカハイドロフォン」と名付けられた。
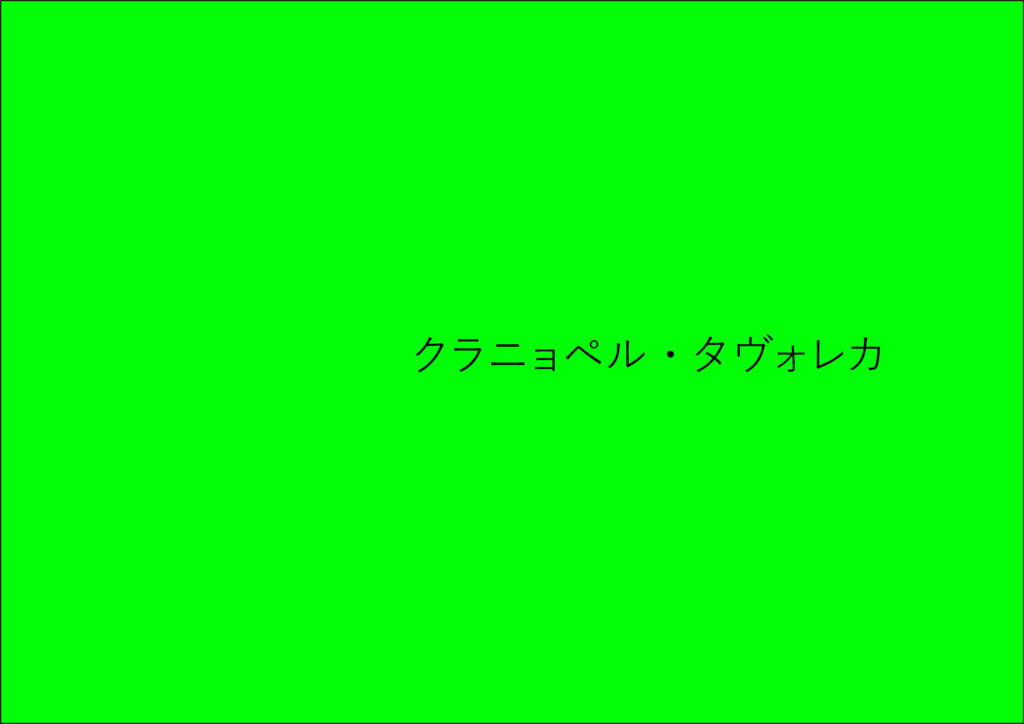
ペンピョラグヌス
造語世界。アーティスト。造語と造語それ自体を会話させることによって、新しい造語を生み出す世界であり、その世界自体がアーティスト。造語の定義は、作者の主観的にわからない言葉とし、被る可能性もあるが、そこはこの世界においては問題にしていない。
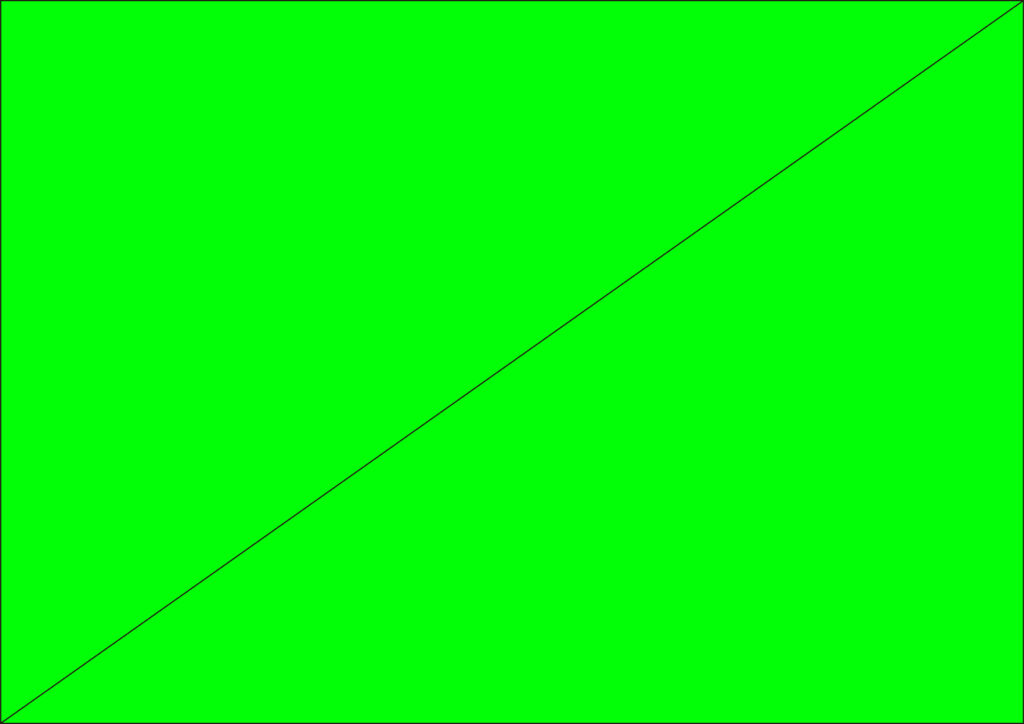
ニャパリナム・ミニョプ
アーティスト。造語翻訳家。造語世界「ペンピョラグヌス」において、発生した造語を「かたち」に翻訳する仕事をしている。時より、自分自身でも造語を制作し、それをかたちに翻訳することによって作品も制作している。しかしながら、完全なる翻訳は造語世界「ペンピョラグヌス」において、不可能であるという立場をとっている。
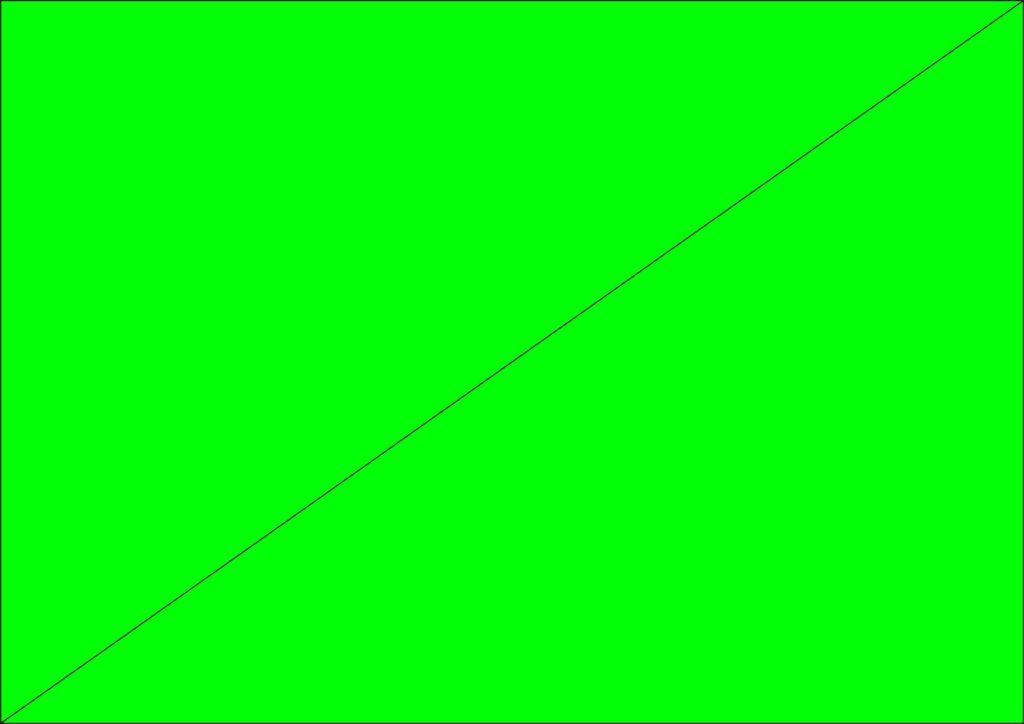
サリューワ・フニョミ
アーティスト。造語世界である「ペンピョラグヌス」において、架空の書物のタイトルを造語によって考案し、発表している。しかしながら、書物に書かれている内容についてどのようなことが書かれているかは誰も知らない。
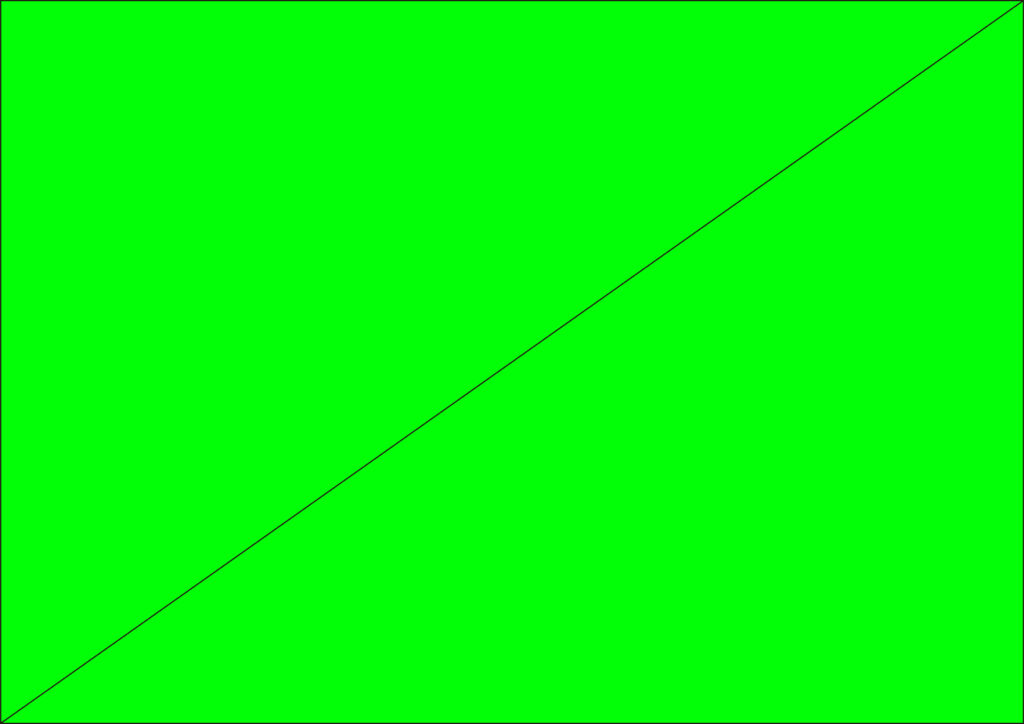
ワヌぺチュア
宇宙。アーティスト。私たちが生きているこの宇宙よりもすべてが過度に存在が存在している宇宙。過有の世界とも呼ばれる。世界を構成している粒子一つひとつが無限の重なりを持つことが原因とされている。この宇宙は、真逆の性質を持つ「無」の宇宙である「ポシュランカ」からいきなり何の理由もなく発生して分岐した。別名は、ニャグリルソンやジンピュールなどと呼ばれる。
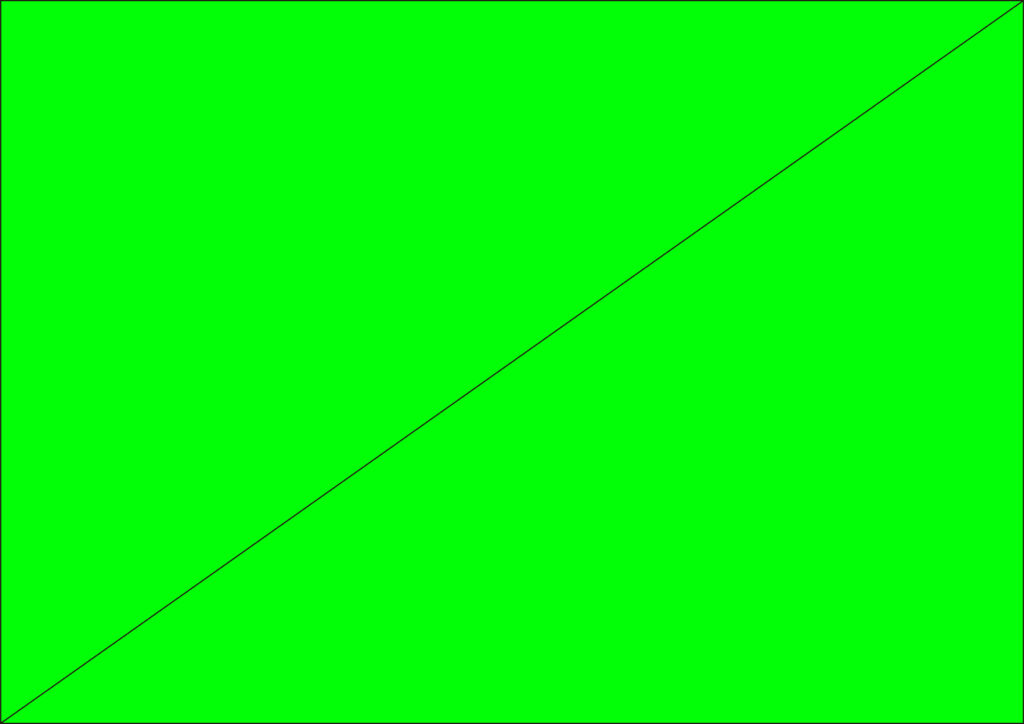
ポシュランカ
宇宙。アーティスト。私たちの生きているこの宇宙ではビッグバンが起こったことによって発生したと言われているが、ポシュランカという宇宙ではすべてが起こっているため結果的にすべてが「無」の状態になっている。空間や時間すら存在していない。私たちの生きている「有」の世界からはアクセスすることができないと言われている。アーティストとして考えられているが、無いということ自体が作品であり、もしかしたら作品ですら無いのかもしれない。
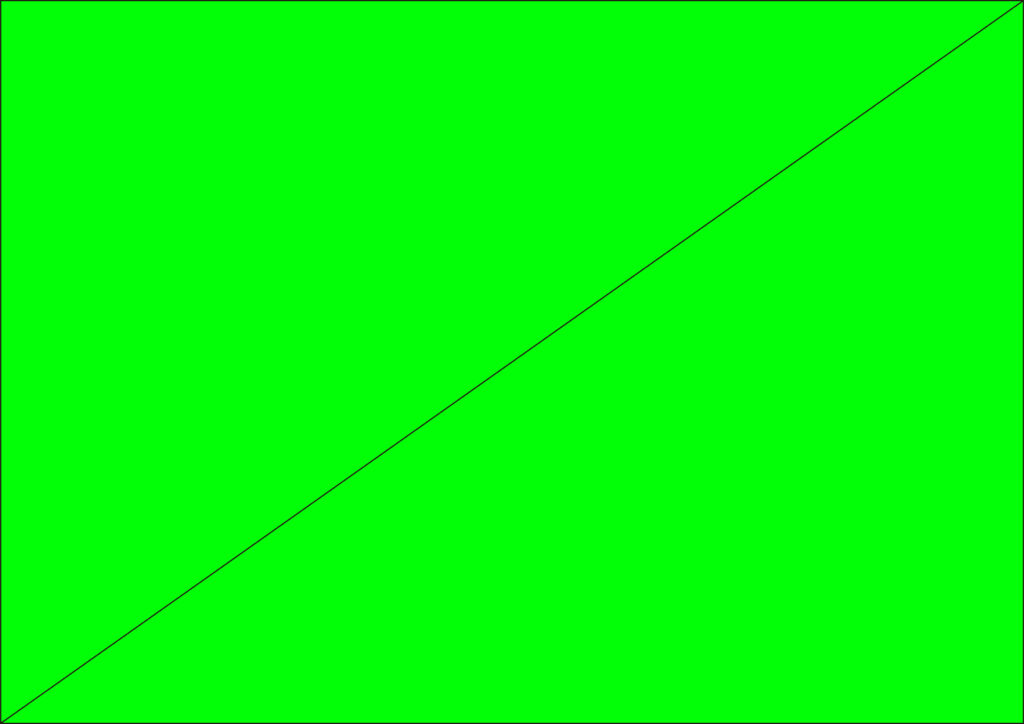
ナジームの炎
炎。アーティスト。2025年にパレスチナのガザ地区で何語でもないような音声のようなものを発している炎をターハー・ナジームにより、路上で発見。のちに「ナジームの炎」と名付けられる。この炎は、世界中の様々な地域に分け与えられ、燃やし続けられている。エレニ・カッサンドリヌによって、音声のようなものを真似ると小石ができることが発見されたり、イマヌエル・フェルマーバイヤーによって、リンゴを燃やすと永遠に燃え続けることが発見されたり、さまざまな未知の可能性がある。
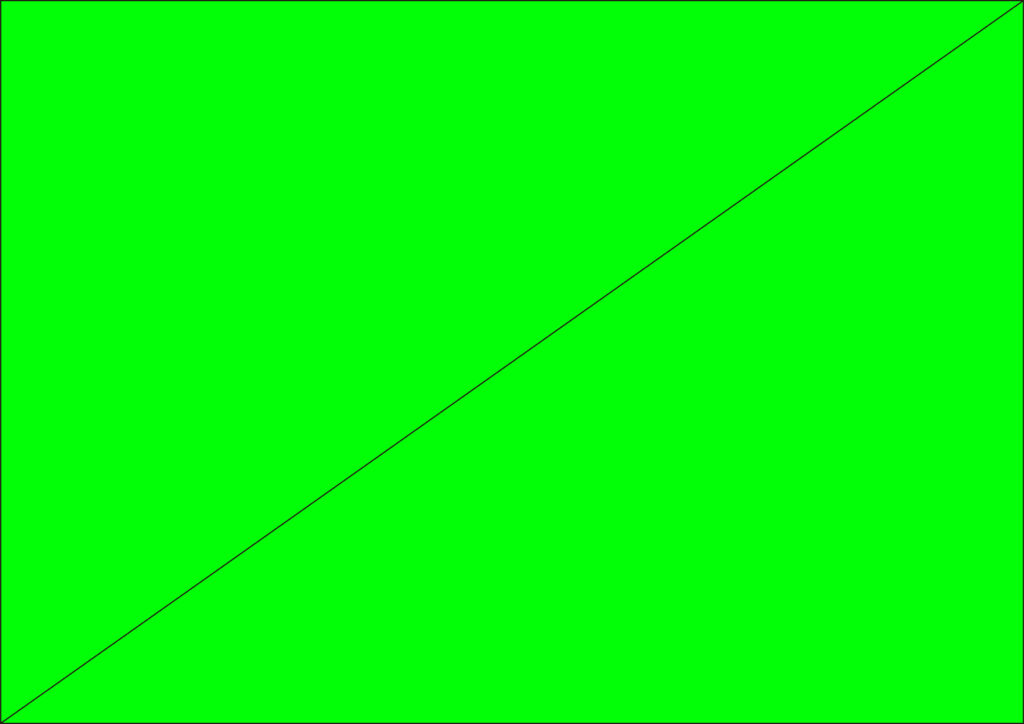
ムウ
カイロス的言語体系。アーティスト。可逆性時間宇宙である「へへ・へペル・へへ」の中で生きる謎の知的生命体群が使用する言語体系。人間の言語のようなクロノス的な線形ではなく、非線形の同時的なカイロス的時間で読み書きする言語。人間の認識能力では理解することが不可能。ムウとは、古代エジプト語で水を意味する。
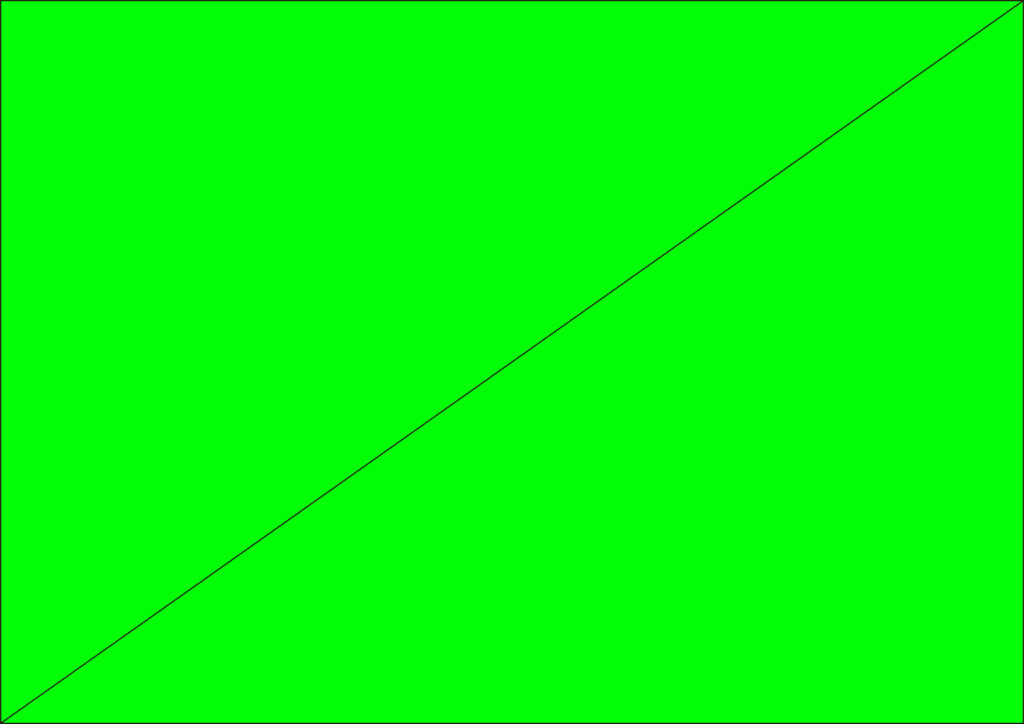
ナフシ
意志を持った惑星。アーティスト。可逆性時間宇宙である「へへ・へペル・へへ」に存在する惑星。意志は、その惑星に近づいたり、上陸したりすることで感じることができる。主な要因は、感覚重力「マスティシュカ」によって引き起こされていると考えられている。ナフシは古代エチオピア語で魂を意味する。
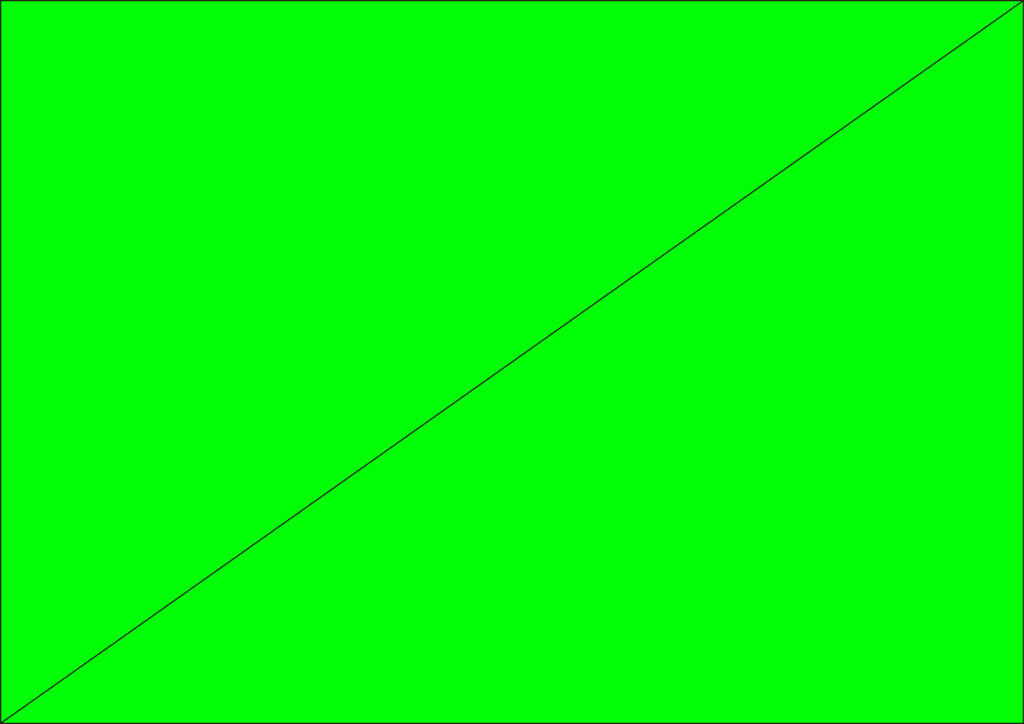
マスティシュカ
感覚重力。アーティスト。意志を持った惑星である「ナフシ」などの惑星に存在する重力のような力の一種。惑星全体の生物や物体に重力のようにその惑星の感覚や気分の影響をおよぼす。マスティシュカは、古代サンスクリット語で脳を意味する。
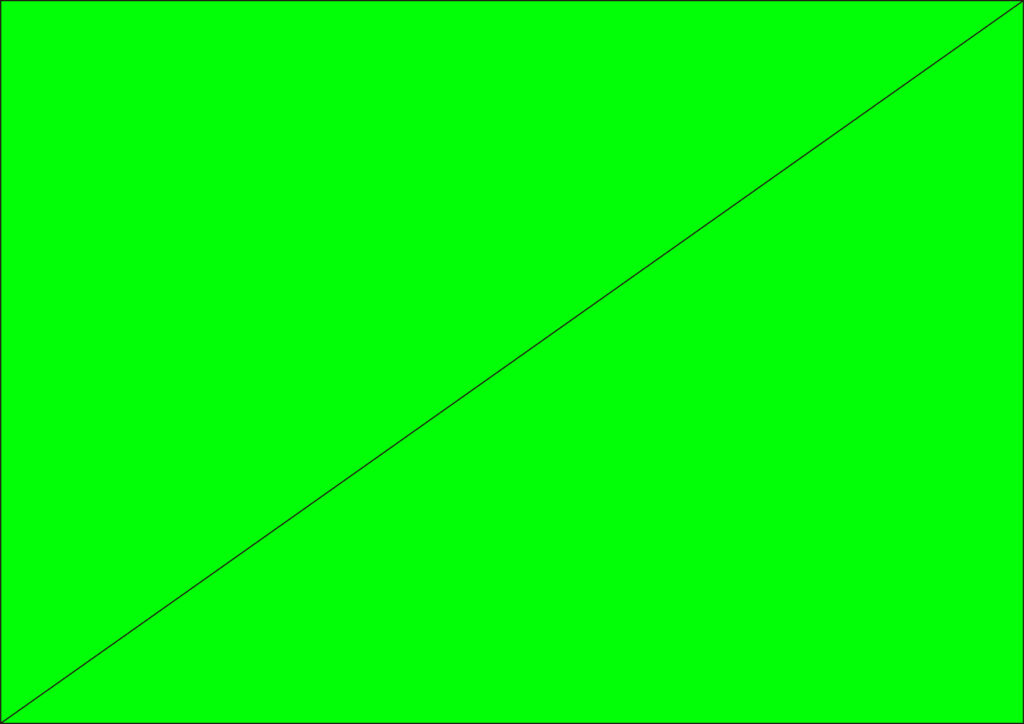
サイラス・モーン
竹林アーティスト。さまざまな不思議な創作竹林を制作。創作によってつくりだされた竹林の竹の一部を切るとその筒状の空間の中から別の宇宙へ行くことができたりする。サイラス・モーンは、アーティストであると同時に、セオドア・ラウシェンバーグのつくりだした人工知能「エレファント」によって人工的につくりだされた超高度な知的生命体でもある。
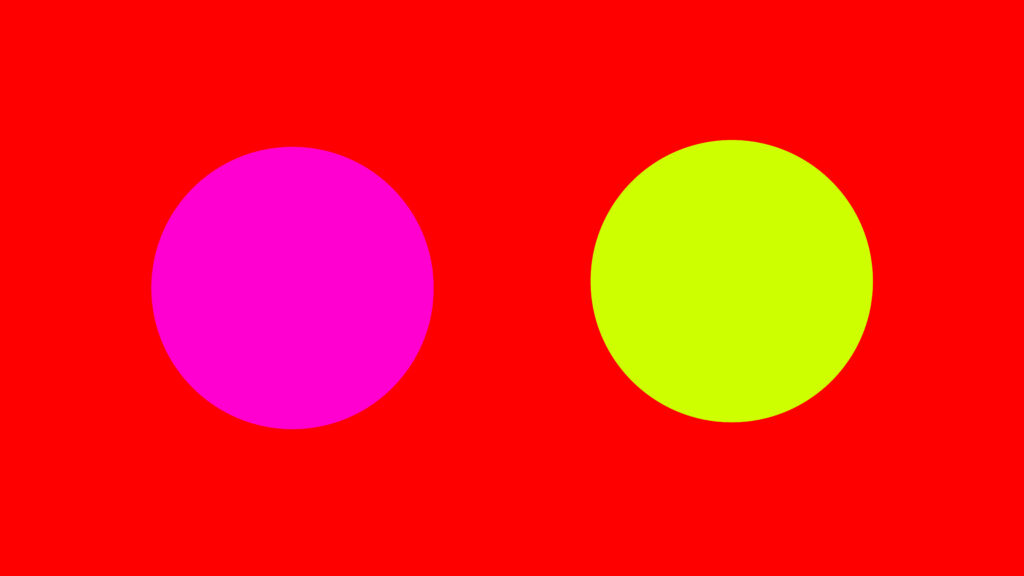
ラネプ
色彩。アーティスト。人間にとっては可視光線の波長の中に存在している。芸術作品や日常生活、そして記憶や想像の中に存在している。また、文化、政治、言語、心理など社会的なものとも密接に関係を持っている。
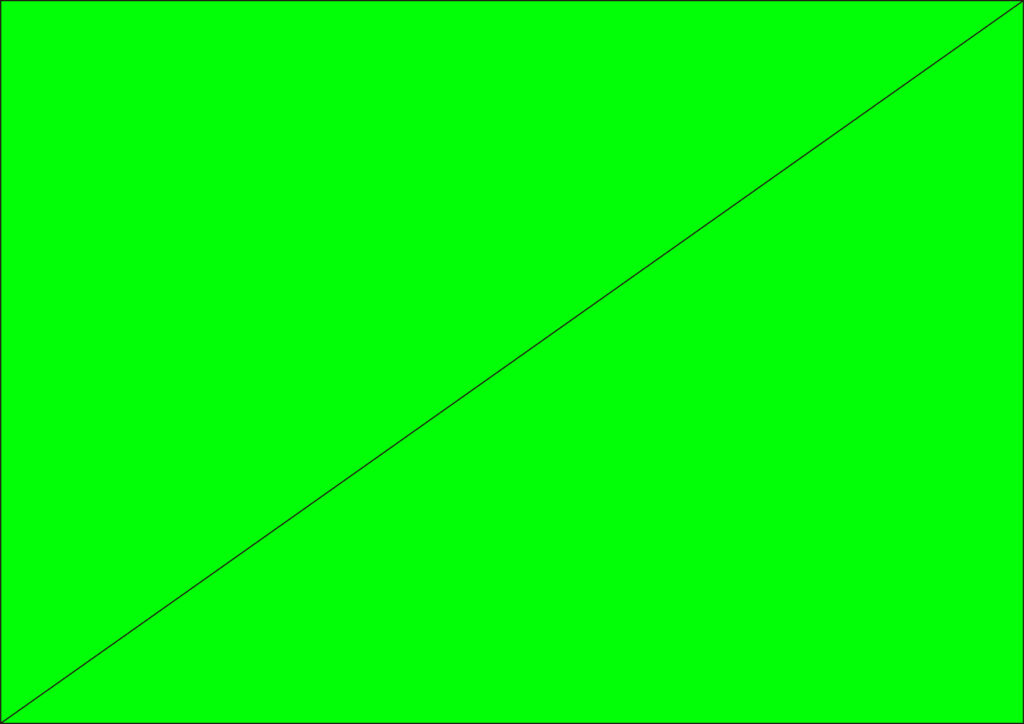
よろすこみ
経済。アーティスト。人類が太古から貨幣を使用し交換することによって、成り立ってきた生産システム。現在の世界はグローバル資本主義が席巻しているように見えるが、実際はさまざまな経済活動を人類は行なってきた。名義としての「経済」は単なる貨幣の流通や市場の論理を超え、物々交換、儀礼的贈与、共有経済、互酬性など、古代から人間社会を支えてきた多様な交換の体系を内包している。
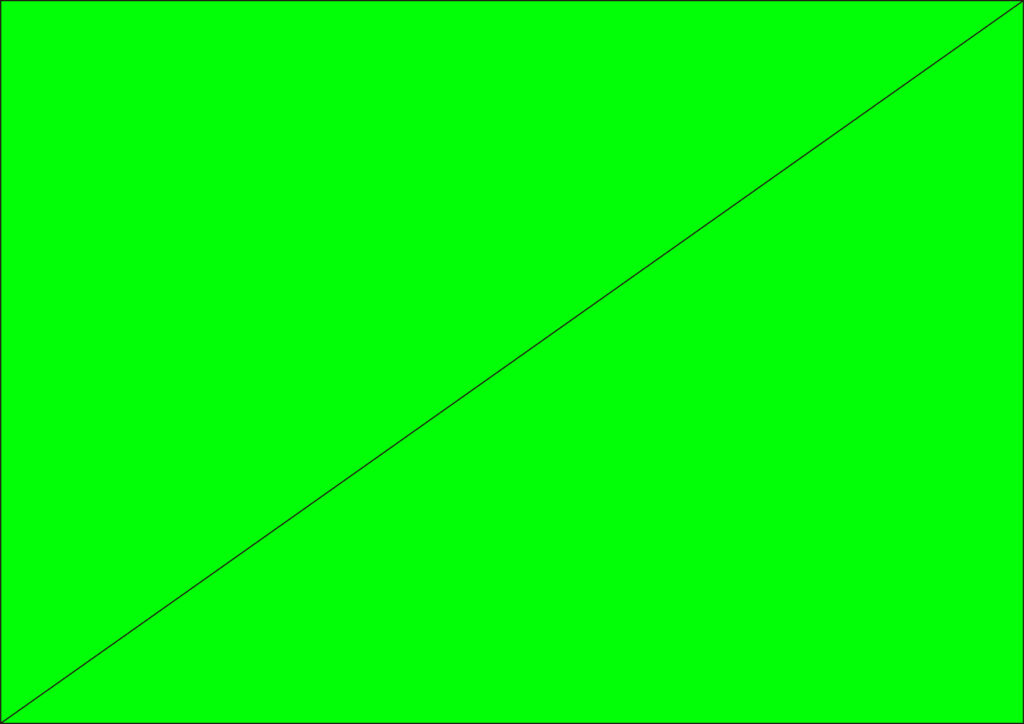
田辺麻穂
彫刻家。一般的に販売されているような工業製品にさまざまな方法で向き合い、手を加えたり「行為を意識」しながら、抽象的な彫刻作品をインスタレーションとして制作する。スーパーボールを使ったおもちゃや折紙による彫刻、ワイヤーによるインスタレーションなど、表現は多岐にわたる。
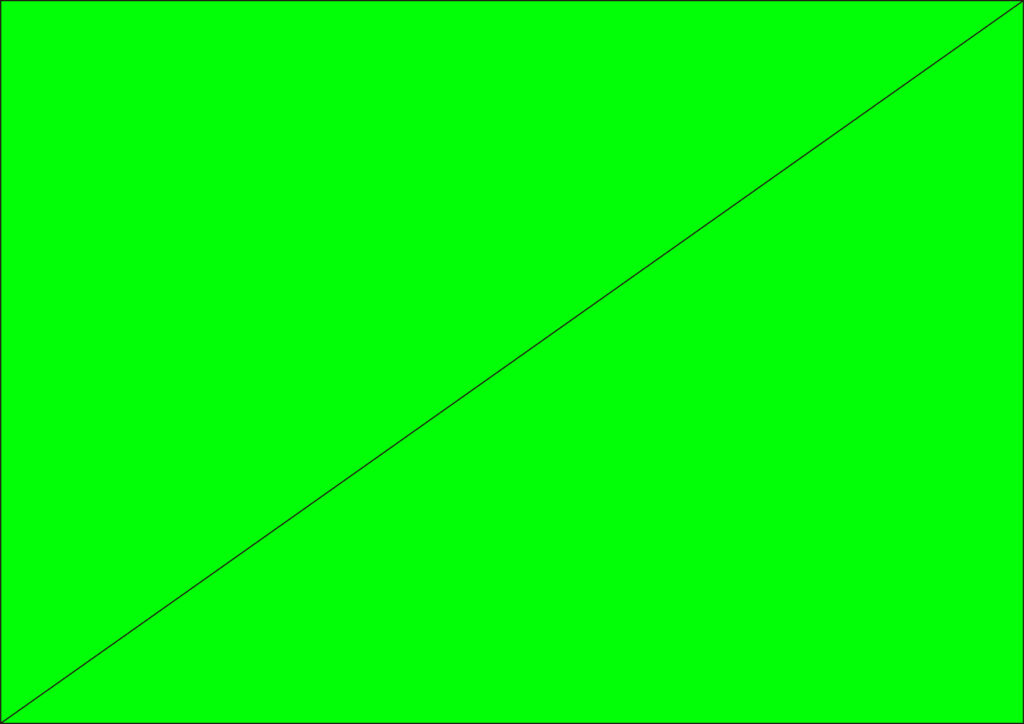
白坂密成
彫刻家。もの派に影響を受けつつも、既存のもの派の主義主張ではなく、あくまで個人的な再解釈として、2025年6月から、木材の廃材のアッサンブラージュなどの制作を開始。
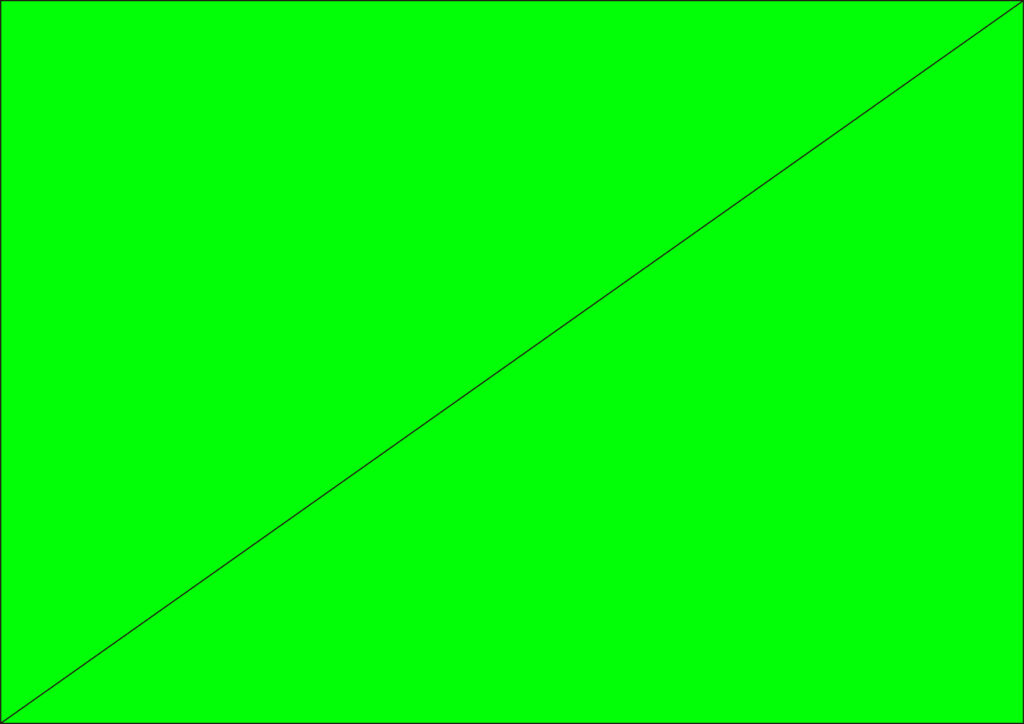
里崎英司
写真家。アーティスト。里崎英司は、既にパブリックドメインとなった写真画像を素材に、再構成・再編集する手法を用いる写真家。インターネットなどで収集した画像を、独自の視点で選び抜き配置などを行いながら、過去の記録に潜む新たな物語を可視化する。展示では、プリント作品だけでなく、インスタレーションやデジタル・スライドショーの形式を取り入れ、観客自身がアーカイブを「再編成する主体」になるような体験を志向している。

マリアナ・コスタ
アーティスト。彫刻家。さまざまな色のフェルトを用いてアッサンブラージュ的なインスタレーションやデジタルでのグラフィカルなアニメーションのシリーズなどを制作している。
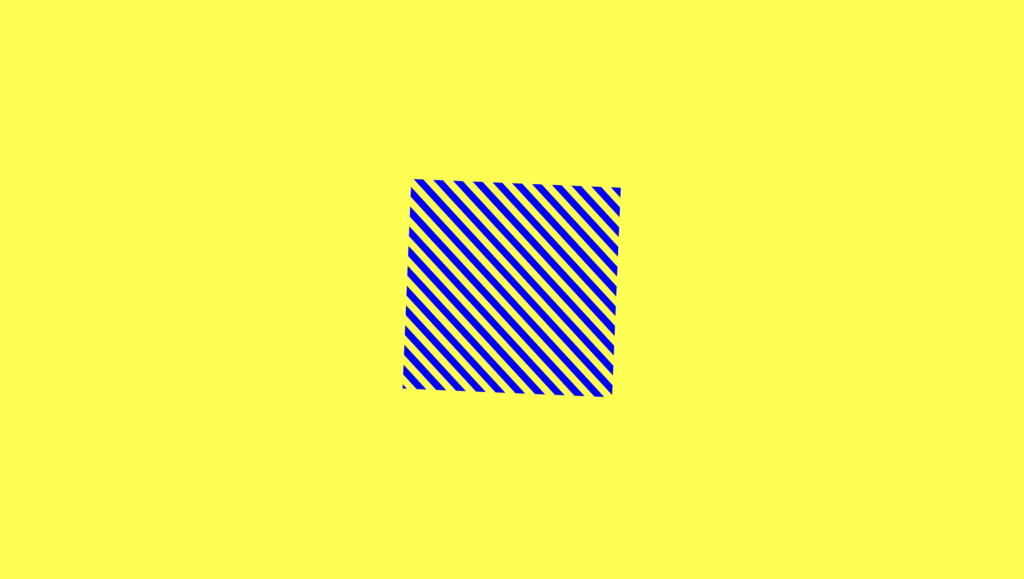
サンジャイ・クルカニ
「HTMLポエトリー」と名付けたHTMLを中心としたコードによるグラフィカルなアニメーションをAIなどを駆使しながら制作している。
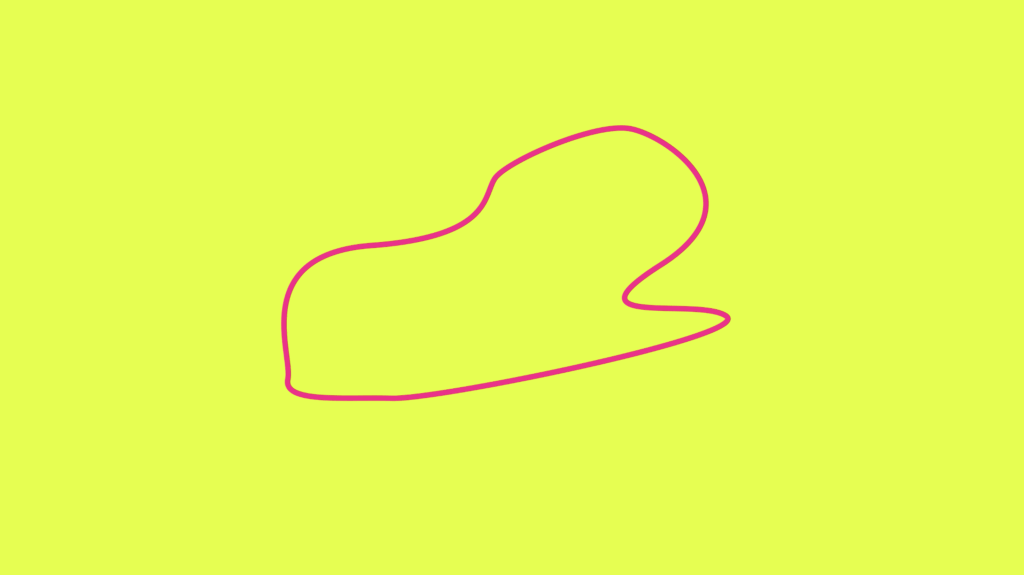
ラレクスヘ
形。アーティスト。様々な物体や記号などありとあらゆるものとして存在している。また、文化、政治、言語、心理など社会的なものとも密接に関係を持っている。ラレクスへとは、ヘラクレスの意味のないアナグラムである。
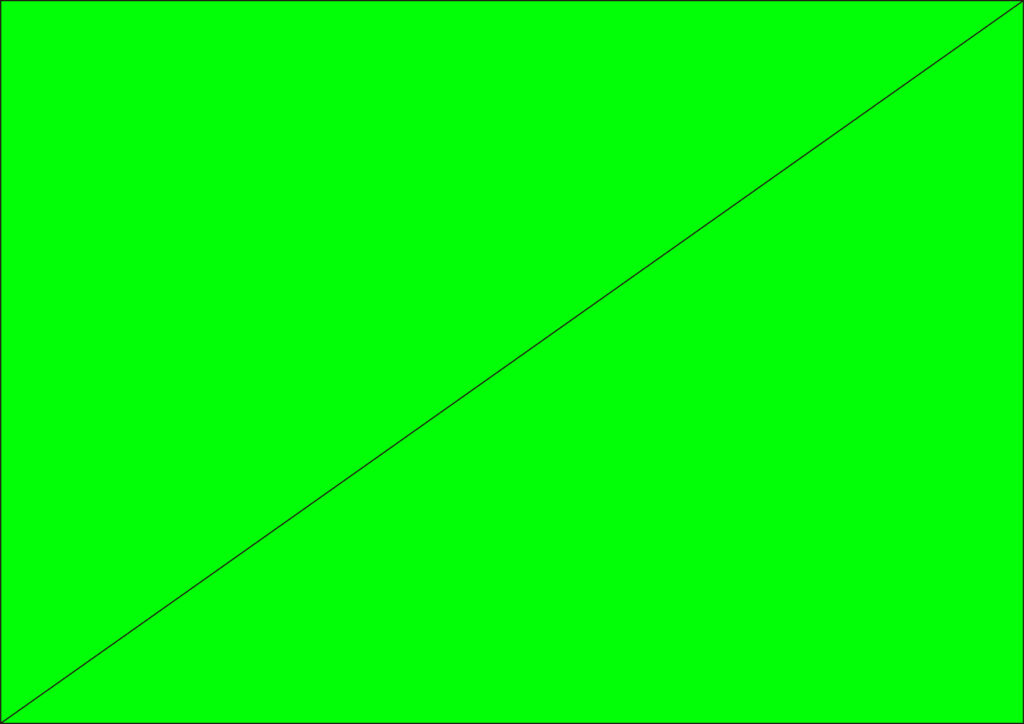
フシスランコンサ
時間。アーティスト。時間という流れ自体がアーティストである存在。様々な表現において根底に流れている。基本形は現在→未来というクロノス的時間というふうに流れている。過去や未来、そして今にだけ着目することもできる。フシスランコンサは、サンフランシスコの意味のないアナグラムである。
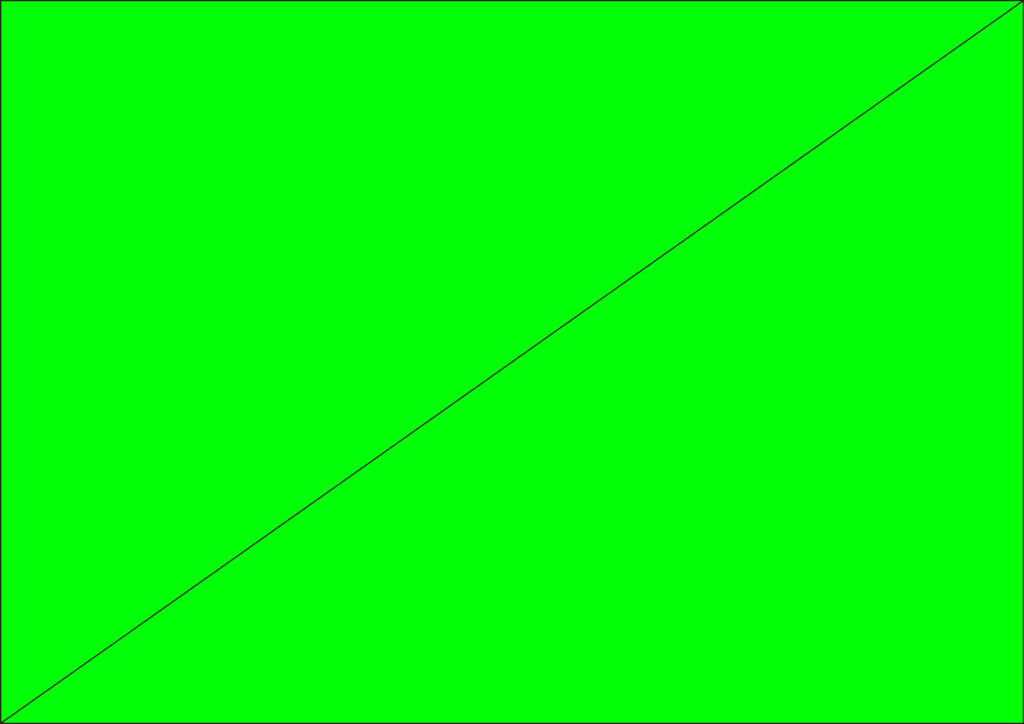
ネラム
思考。アーティスト。人間や動物、AIなどによる思考そのものがアーティストである存在。思考は、内的なネットワークであるばかりでなく、外部と接続しうる開かれたネットワークによる産物であり、このアーティストもそのような存在である。ネラムとは、ラムネの意味のないアナグラムである。

じにゃん
自然物。アーティスト。自然の産物それ自体がアーティストである存在。様々な自然界の事物は人間の時間や空間のスケールを超えて出来上がっている。また、人工物も元を辿れば全て自然との代謝によって出来上がっている。じにゃんとは、にんじゃの意味のないアナグラムである。
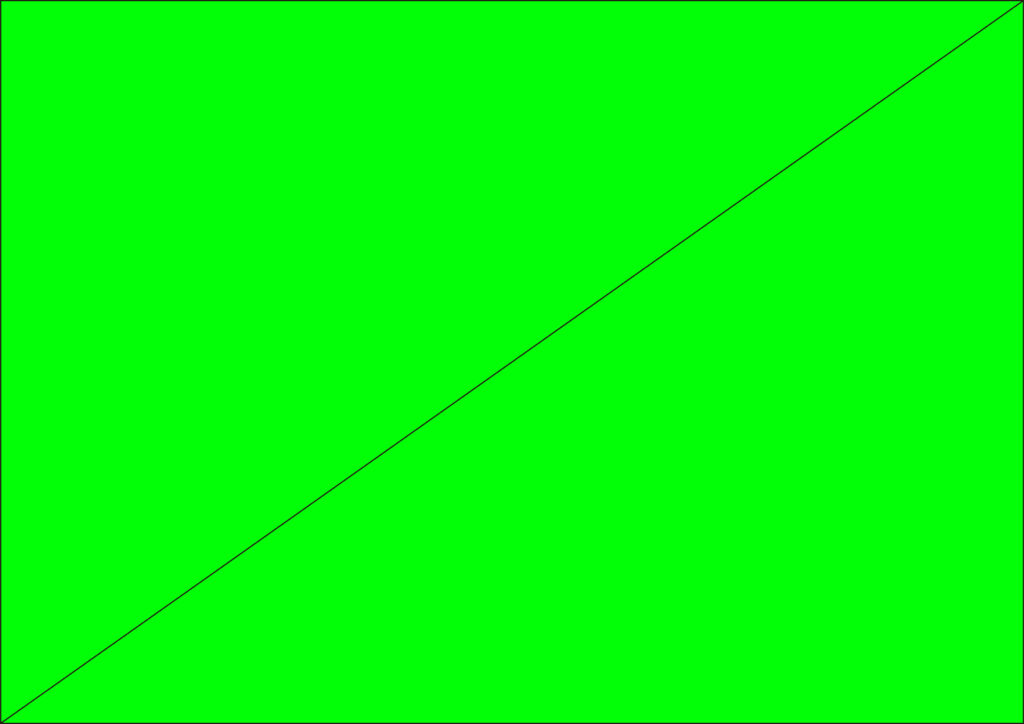
ルダーボン
虚構。アーティスト。本当のことではないことという概念であり、それ自体がアーティスト。フィクションや幻想などとも呼ばれる。人類にとって欠かせない概念であり、人類が文明を築き上げてきた中で重要な役割を担ってきた。芸術や文化の中で特にその活躍は目覚ましい。ルダーボンは、ダンボールの意味のないアナグラムである。
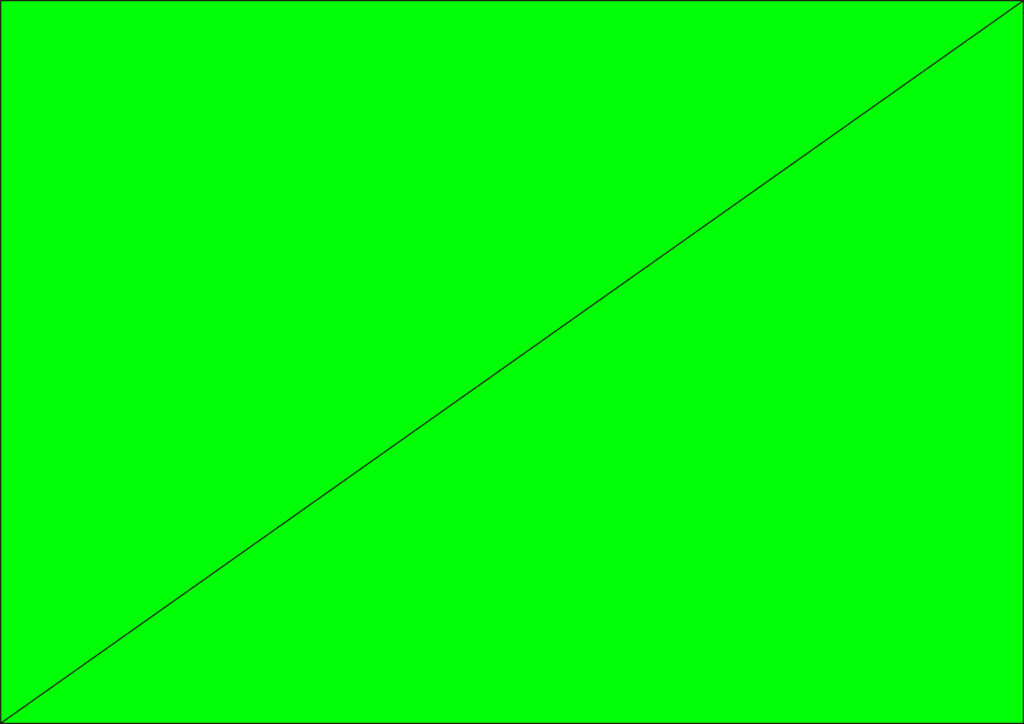
ルユマイセ
変化。アーティスト。一定ではなく、常に揺れうごき、変容し続けることそのものがアーティストであるという現象や立場。生成変化、プロセス、流転、進化、退化などとも密接に関係する。ルユマイセとは、マルセイユの意味のないアナグラムである。
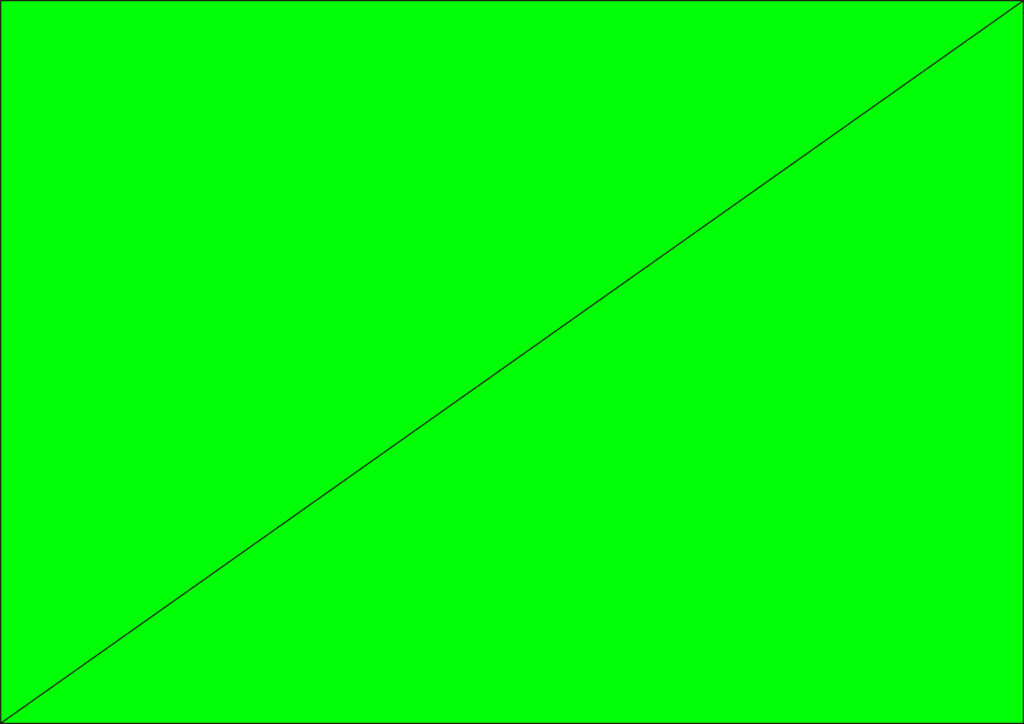
ステムダムアル
境界。アーティスト。あるものと別のものを隔てる「境界」こそがアーティストであるという存在。内と外、生と死、光と闇、自己と他者、現実と虚構など、様々なものの狭間で表現を生成する。ステムダムアルとは、アムステルダムの意味のないアナグラムである。
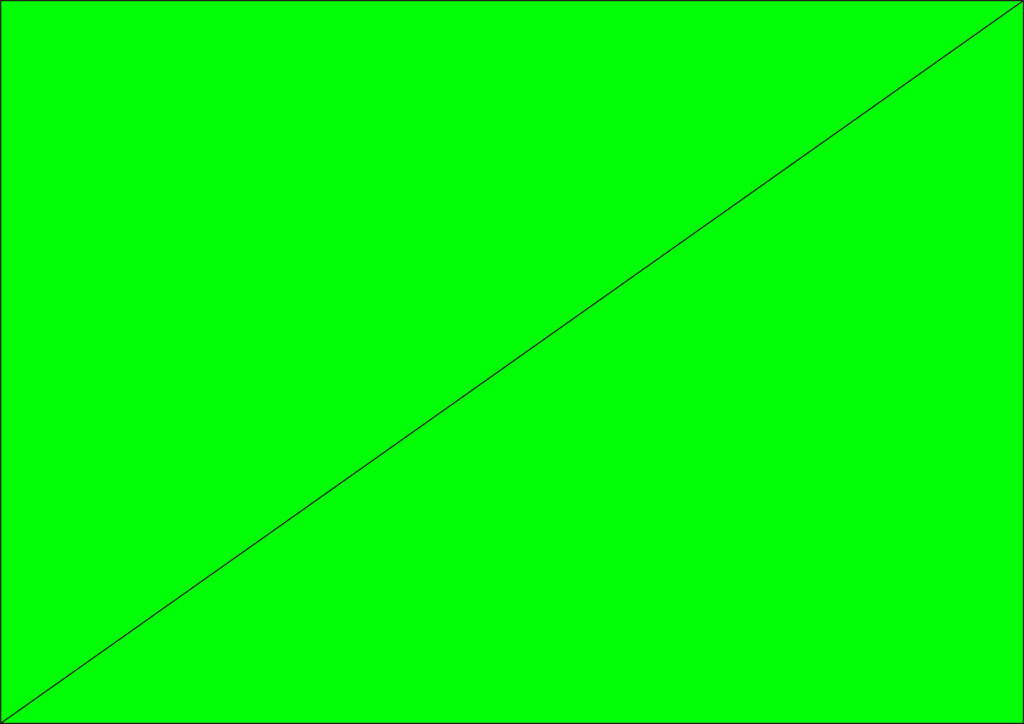
ナッレソペー
遊び。アーティスト。人類の文化の根源でもあり、願望でもある。遊びは文化に先立って存在している。子ども、動物、神話、夢、偶然、無意味などといったものと親和性が高い。作品は、しばしば誤解され、破壊され、再発見される。ナッレソペーとは意味のない造語である。
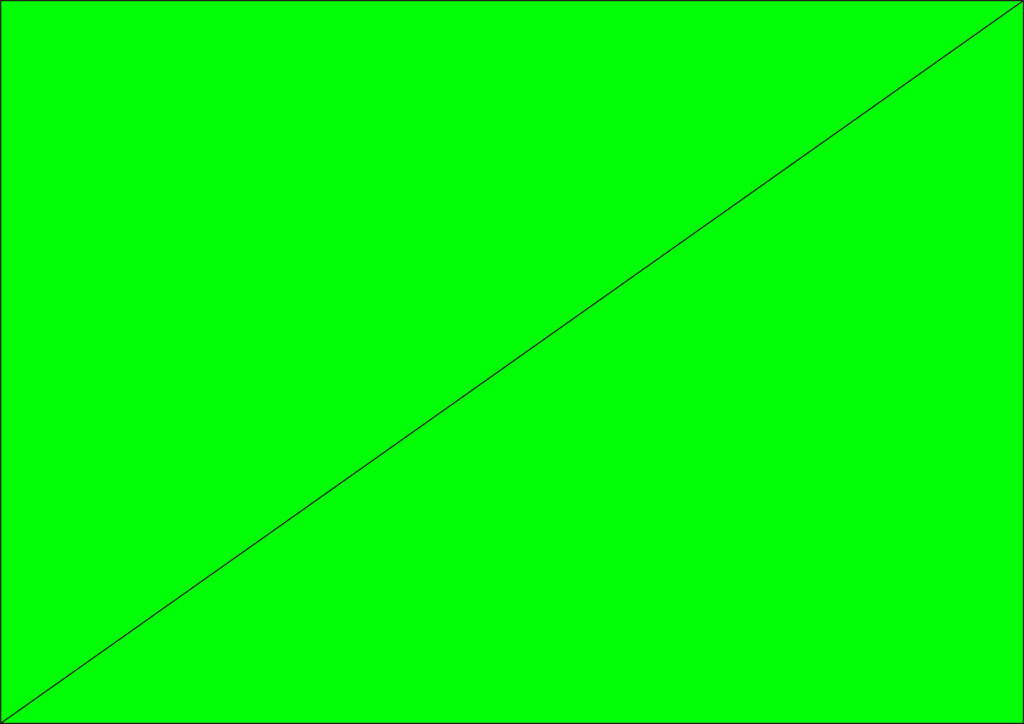
グリ
文字。アーティスト。古今東西の様々な言語で使われている表記媒体。グリには、手書きの文字から活字のフォントまで様々な文字を含む。
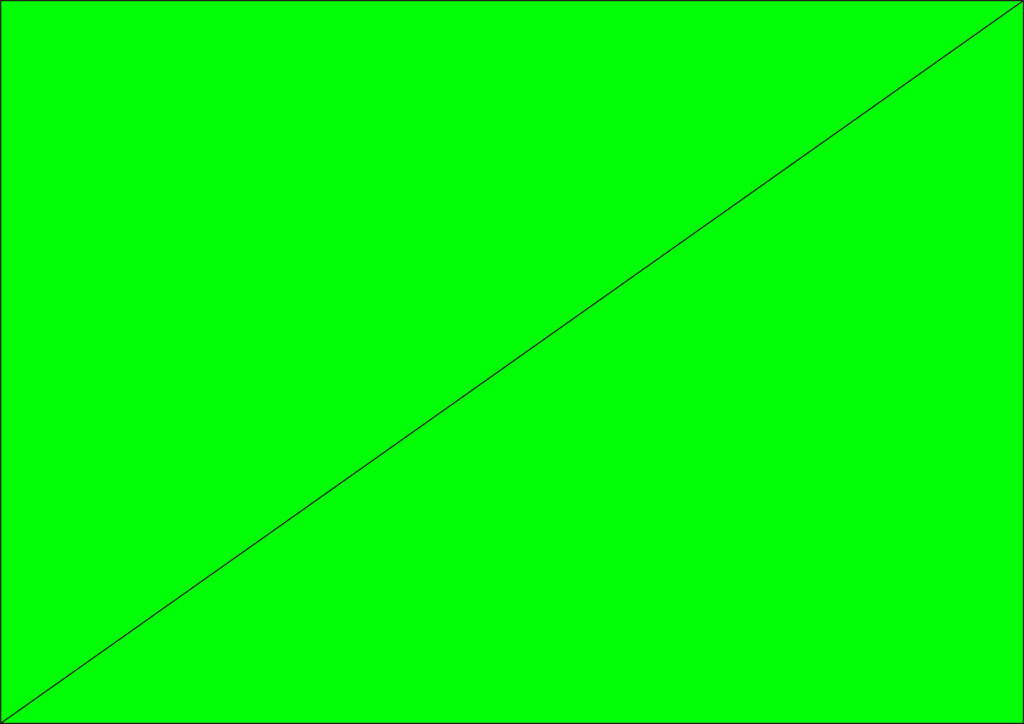
アウィス・ララ
ポストカード。アーティスト。1869年にオーストリア=ハンガリー帝国のエマヌエル・ヘルマンによって提案された世界初の郵便はがきから始まったはがきというフォーマットの郵便用紙。日本のフォーマットでは、サイズ:縦148mm × 横100mm(JIS規格)が基本となっている。実用品から始まり、観光・アート・記念品としての役割を拡大し、デジタル時代には物質的な魅力や収集価値が際立つメディアへと変化してきた。アウィス・ララはラテン語で珍しい鳥を意味する。

エムレハン・サルバン
アーティスト。Friendly Galleryディレクター。Friend Galleryは、このCream Soda Museum内に存在するオンラインギャラリーである。
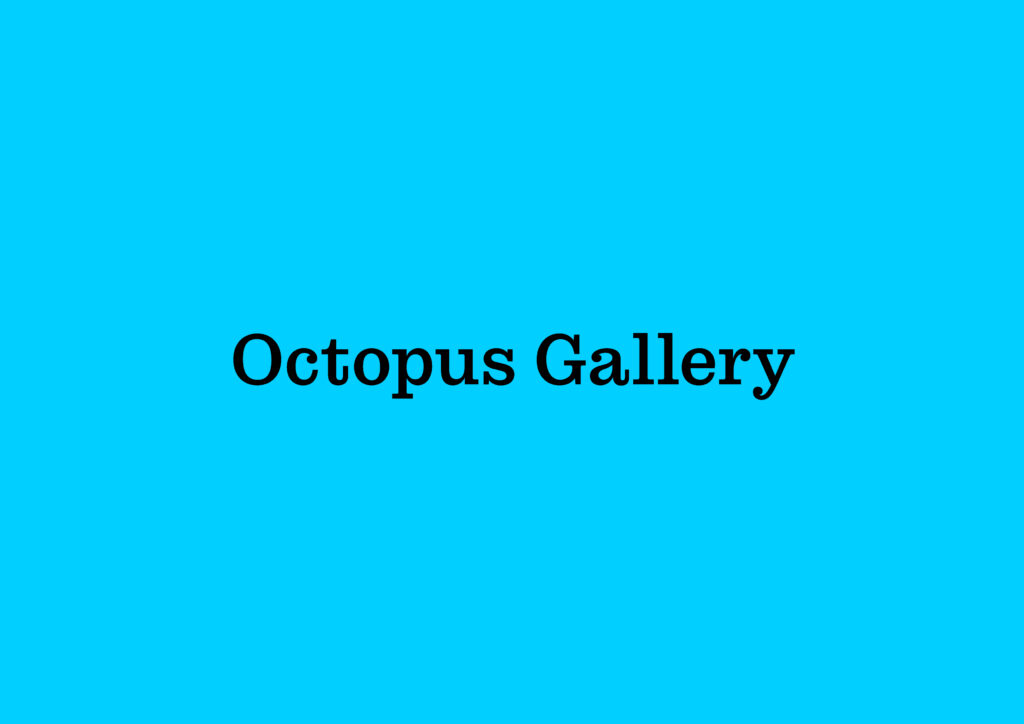
フリオ・アンドレス・モンタルボ
アーティスト。Octopus Galleryディレクター。Octopus Galleryは、このCream Soda Museum内に存在するオンラインギャラリーである。

ナティア・ゴゴニシュヴィリ
アーティスト。Magical Galleryディレクター。Magical Galleryは、このCream Soda Museum内に存在するオンラインギャラリーである。

じゃじゃ
食料。アーティスト。人類が食べることができる素材、もしくはそれらによる調理品(料理)。じゃじゃは、人類の文化の中でも重要な役割を担ってきた。
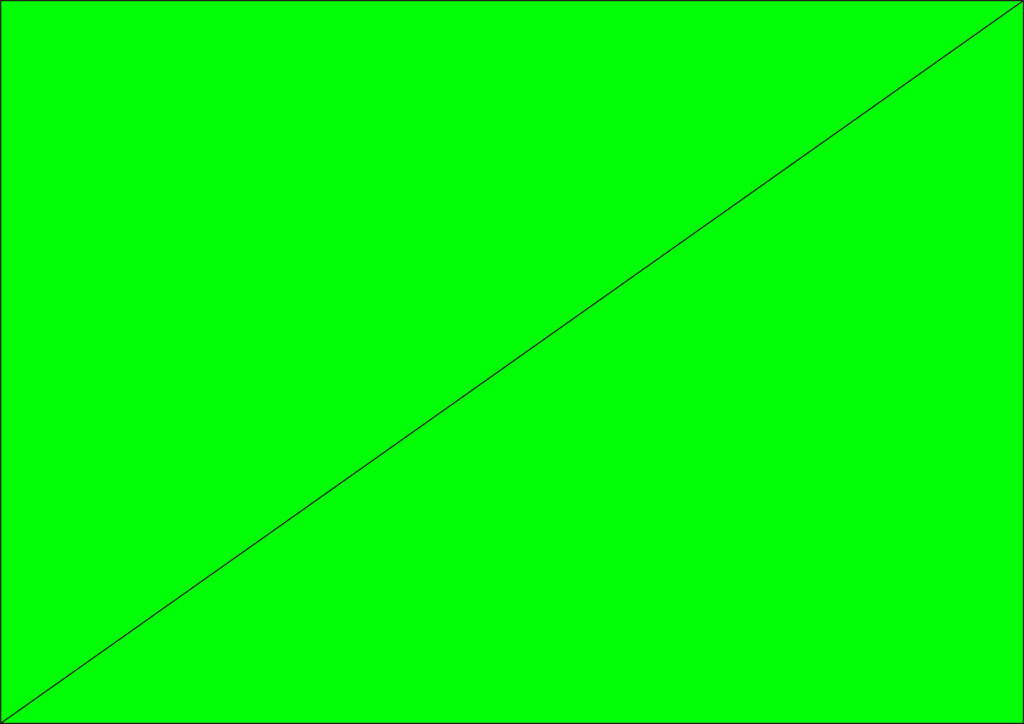
ぐら
キュレーション。アーティストキュレーター。作品や情報を選び、組み合わせ、意味をもたせて提示する行為一般。美術館では主に展示企画のことを指し、ネットや日常では情報やモノを編集・整理して共有することも含む。
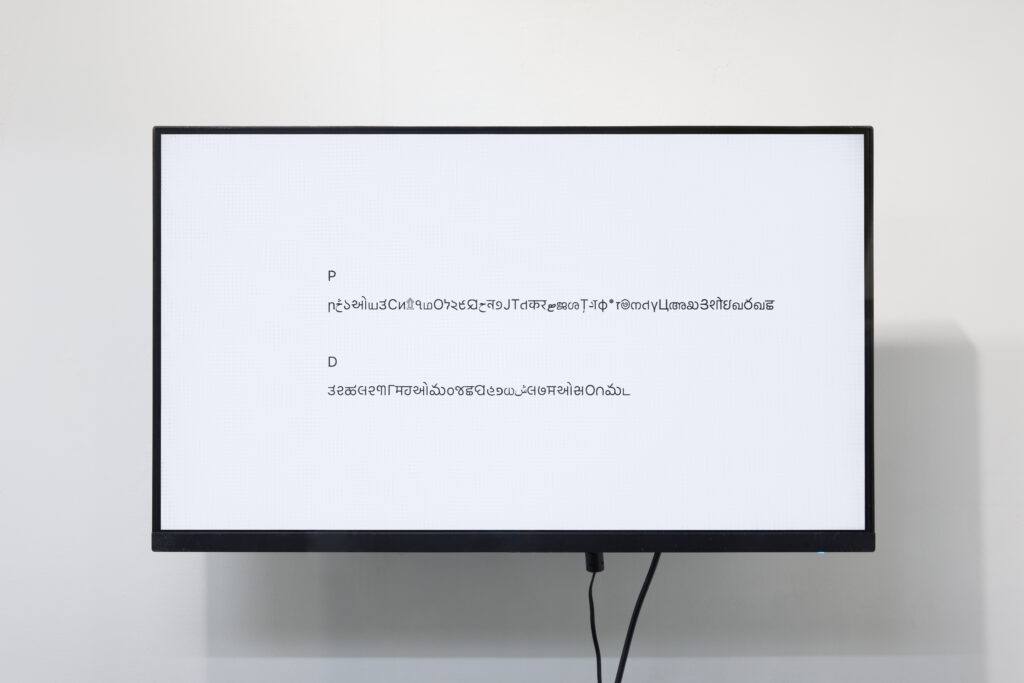
キャロットランゲージ
様々な世界中の言語の文字を一文字ずつ並べ替えて、意味が全くわからないようにしてつくる人工言語。アーティスト。最初、言語をモチーフにした脱コミュニーケーションをテーマに活動する作家のGAME82のプロジェクトとして発表されたが、そこから2025年作家として自立した。
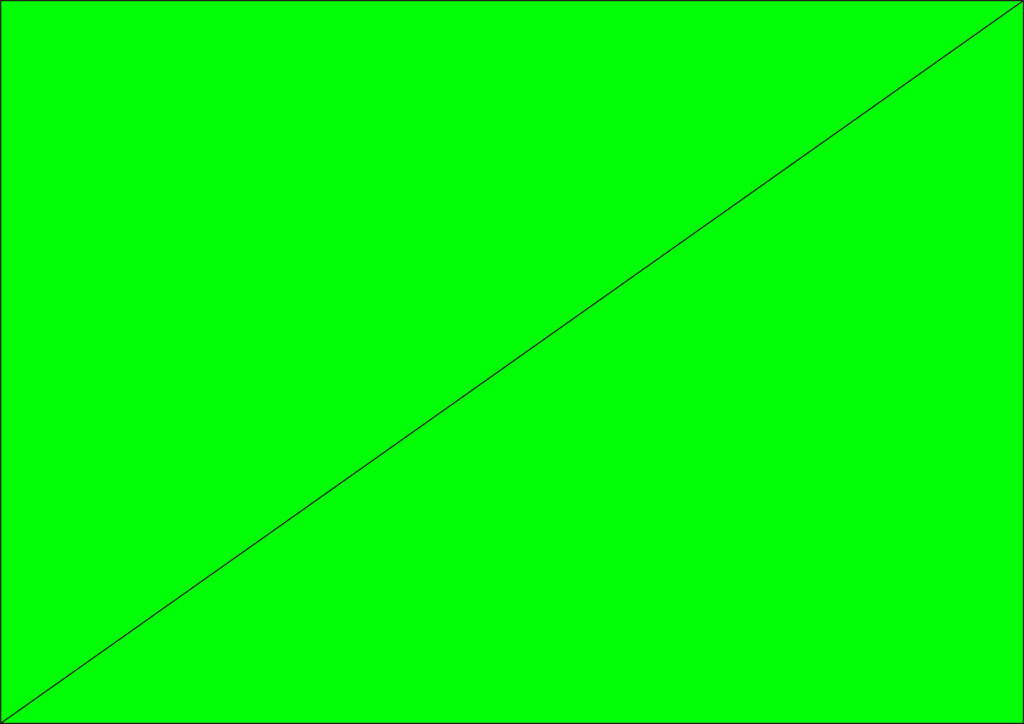
ピラトゥム
制度。アーティスト。社会を形づくる仕組みそのもの。法、教育、宗教、政治、美術、日常など不可視の枠組みが表現を生成する。ピラトゥムは、一見、現実を形づくっている強固で変わらないシステムのように思えるが、実際は人類は、ピラトゥムを遊びながら柔軟に形づくってきた。

ミティカ
風景。アーティスト。自然や都市、またそれらが織り混ざった場やそれらを見る視点。ミティカは、あるときは観光地や名勝として制度化されたり、戦争や災害によって劇的な変貌を遂げたり、開発や資本の論理によって開拓されるなど、常に人間との関係性の中でも変化してきた。
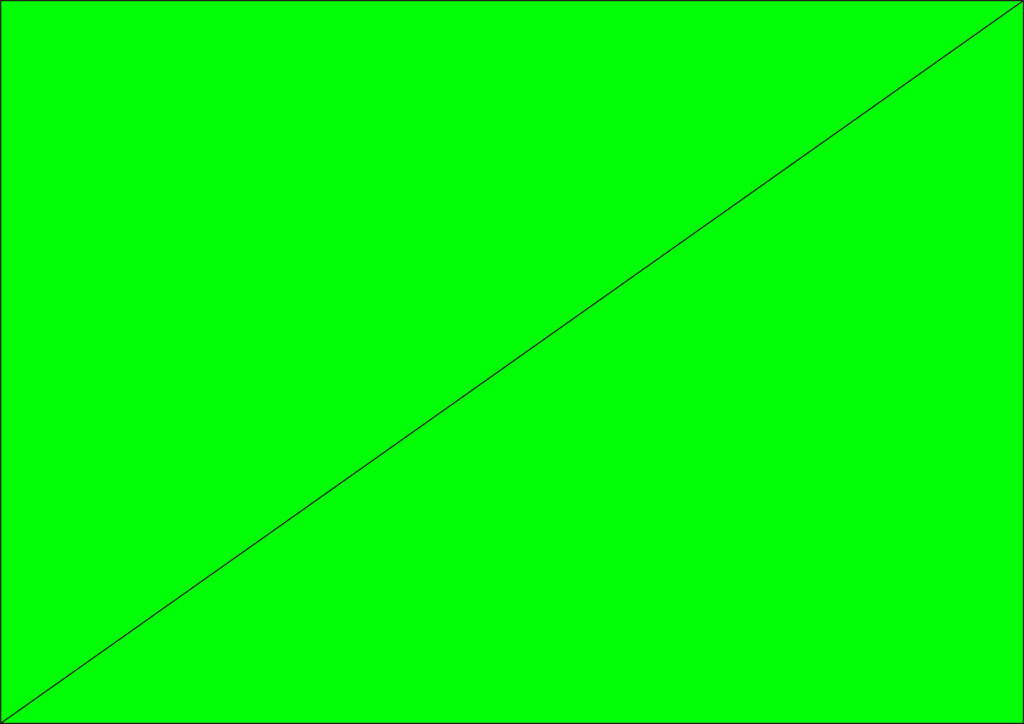
フルーア
空間。アーティスト。日常用語としてはある大きさを持った入れ物。3次元ユークリッド空間では、すなわち、すべての方向に無限に拡がる果てしのない均質な空虚な容器。縦と横、前後、左右、上下などフルーアの関係に関する言葉はたくさん存在する。
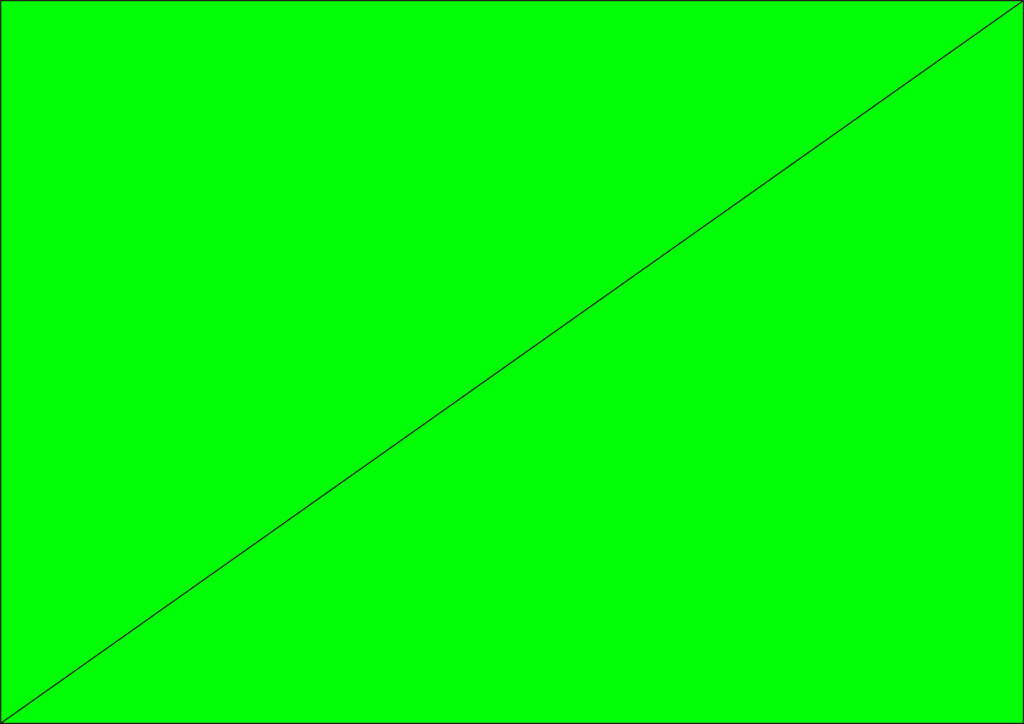
スルート
風。アーティスト。空気の流れのこと、流れる空気自体のこと、またそれによる現象。古来、風という言葉は眼には見えないものを象徴するために使われてきた。日本においては、風神のように伝承や信仰において神格化されることもある。
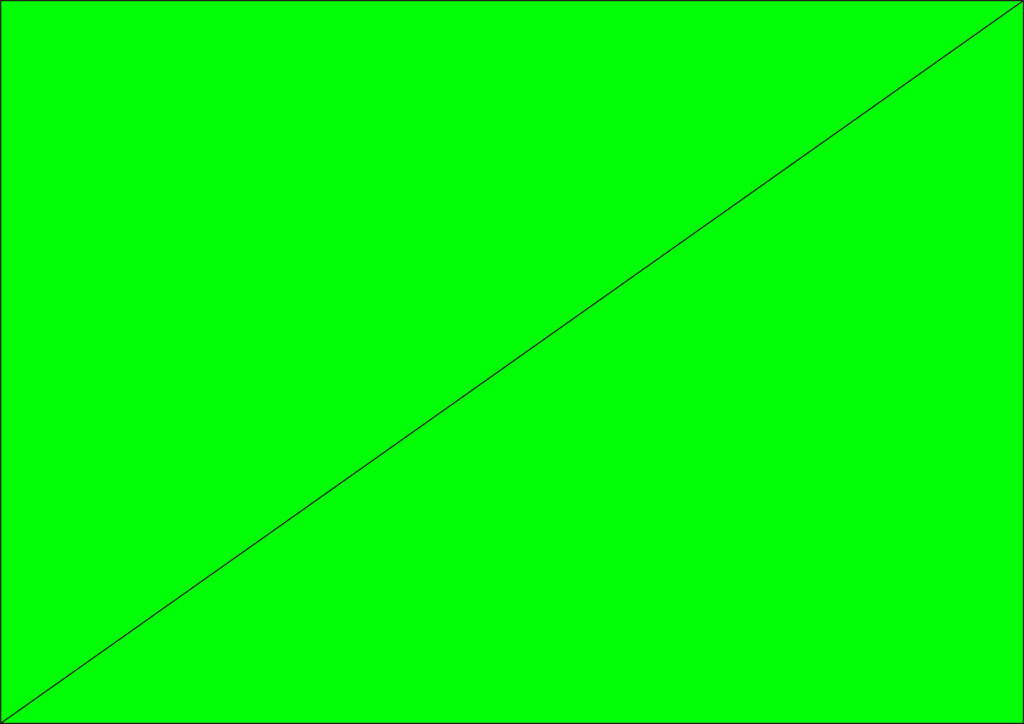
ピング
音。アーティスト。ものや声などによって引き起こされる響きが耳に届いて聞こえるもの。音響とも呼ばれる。生物にとっては、様々なコミュニケーションの手段として用いられている。音による芸術文化は、音楽と呼ばれる。